ニュース&イベント NEWS & EVENTS
未来のLCD技術の進展へ:新しいIGZO‐11半導体の大型単結晶の合成に成功 ~表示速度や解像度の改善・向上、画面サイズの大型化に大きく寄与する方法論を確立~

東京理科大学
ソノラ大学
- ●液晶ディスプレイに用いられる新材料、IGZO(イグゾー)の一タイプであるInGaZnO4(IGZO-11)のセンチメートルスケールの大型の単結晶の合成に成功しました。
- ●IGZO-11は透明性と導電性の両方を兼ね備えた半導体としてオプトエレクトロニクスデバイスへの応用が期待されていますが、その物性には未知の部分が多い上、物性研究に必要な大型の単結晶の合成にはこれまで成功していませんでした。
- ●この研究成果は、将来的にタッチディスプレイや有機LEDなどの透明オプトエレクトロニクスデバイスへの応用が期待できます。
酸化物半導体In-Ga-Zn-O(一般表記はIGZO、通称イグゾー)はインジウム(In)、ガリウム(Ga)、亜鉛(Zn)を含む酸化物半導体で、液晶ディスプレイや赤外線センサー、太陽電池などの分野に応用される将来性のある物質として注目されています。1985年に日本で初の合成に成功して以来、IGZOを使った薄膜トランジスタ(TFT)はフラットパネルディスプレイのバックプレーンとして使用されてきた歴史があります。宮川宣明教授の率いる東京理科大学グループは、東京大学の藤井武則助教、メキシコ・ソノラ大学の君塚昇客員教授らとの共同研究により、この度新たに、In-Ga-Zn-Oの特定のタイプであるInGaZnO4(IGZO-11)の、センチメートルスケールの大型の単結晶の合成に成功しました。IGZO-11はワイドバンドギャップ、高い電気移動度、導電性などの魅力的な特性を持つ半導体で、将来的にタッチディスプレイや有機LEDなどの透明オプトエレクトロニクスデバイスへの応用が期待できます。
【研究の背景】
IGZO研究の原点は1985年にあります。現在の国立研究開発法人物質・材料研究機構の前身であった無機材質研究所の君塚昇氏が、一般化学式(InGaO3)m(ZnO)n (m, n =自然数;以下、IGZO-mnと表記)のIGZOセラミックス多結晶体を開発したことが始まりです。当時は、エレクトロニクス業界がこの金属酸化物から製造された薄膜トランジスタ(TFT)をライセンス供与し、タッチディスプレイなどのデバイスに応用するようになるとは誰も考えなかったでしょう。現在ではIGZO薄膜の研究は精力的に行われていますが、その一方で、この物質の大型バルク単結晶の育成は容易でないために、現在でもIGZO結晶固有の物性には、様々な不明点が残されています。良質な単結晶育成法が確立され、この物質の基礎特性が明らかにされれば、様々なデバイスの改良にもつながるものと思われます。
通常金属は多数の自由電子を有した良導体であり、光を当てると、自由電子が外部光(電磁波)と共振し、光波は遮蔽されて反射されます。金属が透明ではなく、金属光沢をもった優れた導体であるのはこのためです。対照的に、IGZOは大きなバンドギャップを有する半導体であるため、可視光範囲内であっても光を透過することができます。大きなバンドギャップを持つ物質は絶縁体であることがほとんどですが、IGZOのような大きなバンドギャップを有する半導体材料では、酸素欠陥を使用してキャリアを注入することで、透明でかつ導電性のある材料を生み出すことができます。
透明性と導電性の両方を兼ね備えた半導体は、オプトエレクトロニクスデバイスでの使用に適しています。さらに、IGZOベースのトランジスタでは、高い電子移動度、広域にわたる均一性、低い処理温度などの利点が加わるため、高エネルギー効率かつ高解像度を達成することが可能です。さらに、フォンノイマン型コンピュータ、つまりデジタルコンピュータは、基本構成要素として電気回路の「オンオフ状態」を必要とし、理想的な「オフ」状態は「ゼロ」電流に対応していなければなりません。IGZO-11のオフ電流値は極めて小さく、エネルギー損失を最小限に抑えられる点でも非常に優れているのです。
しかし、デバイスの改良および新規デバイスの考案・開発に必要不可欠となる物質固有の性質を明らかにするためには、良質なIGZO-11単結晶による様々な物性測定を行う必要がありますが、十分なサイズのIGZO-11の単結晶は未だ合成に成功しておらず、その本質的特性については解明されていません。東京理科大学の宮川教授を中心とする研究チームは、IGZO-11の特性を解明することを目的として、この種の単結晶を成長させる新しい技術を開発しました。
【研究方法の詳細】
多成分系層状物質の合成における主な課題は、結晶成長時の欠陥形成です。さらに、この物質の物理的・化学的性質は未知であったため、結晶を育成する過程で細心の注意を払う必要がありました。研究チームは、IGZO-11が大気圧下では分解溶融型物質(すなわち、結晶性固相は溶融過程で元の組成とは異なる組成を持った第2の結晶相と液相に分解される物質)である可能性があるという事実を踏まえ、単結晶を作るために光学式浮遊帯域法(OFZ)を選びました。気圧を上げることで蒸発や気化を抑え、液相から良質の単結晶を成長させることに成功しました。
OFZを使うことにより、容器を必要とせずに高品質の酸化物単結晶を成長させることができるため、液体材料が受ける温度および圧力に対してより確かな制御が可能となります。さらに研究チームは、合成にZnリッチの供給ロッドを使用することで、Zn欠損のレベルを制御することができました。
単結晶の合成に成功すると、さらに研究チームはその物理的性質を調べました。育成された単結晶は青みを帯びていますが、酸素雰囲気中でのポストアニーリング処理により、結晶は透明になりました。結晶中の酸素欠陥によって生成された電子キャリアは、赤色光を吸収して青色光を放出します。従って、研究者らは色の変化を、単結晶がアニーリングされるときに、この酸素が空孔を満たすことと関連付けました。
さらなる物性の解明のために、研究チームは単結晶の電気伝導度、移動度、キャリア密度の温度依存性を測定しました。その結果、酸素雰囲気下でのアニールにより電気的特性を制御できることを突き止めました。ポストアニールによって、室温でのキャリア濃度と導電率が1017〜1020 cm-3及び1~2000 S cm-1の範囲内で制御することができました。また、キャリア密度が増加すると移動度が増加することを報告しています。この特性はいくつかのIGZO-1n薄膜の伝導性研究で以前から注目されており、この異常な挙動がIGZO-1n類の本質的な特徴であることを示唆しています。
研究チームは、単結晶のc軸(層状構造の各面に垂直な軸)に沿った導電率がab面(層の面)の導電率よりもかなり小さく、異方性はキャリア密度の減少と共に増加することにも注目しました。宮川教授は次のように説明しています。「c軸に沿ったインジウムとインジウムの距離は、ab面に沿った距離よりはるかに長くなります。したがって、波動関数の重なりはc軸方向で小さくなるのです」。電子軌道の波動関数の重なりの程度は、電子がどれだけ容易に動くことができるかに影響を与えます。研究グループは、これがIGZO-11結晶の異方性導電率の要因である可能性を示唆しています。
【今後の展望】
これまでIGZOはスマートフォンやタブレットなどに応用され、人々の生活を変えてきました。最近では、大型のOLEDテレビなどの液晶ディスプレイでも使用されています。今後さらにIGZOの物性を理解し、広い分野に応用していくためにはさらなる材料の良質化と大型化の必要性はありますが、この研究で大型単結晶育成手法を確立できたことは、透明導電性基板やパワーデバイスの分野など多くの応用分野で利用できる可能性を生み出しました。LEDに直接適用できるIGZO-11からトランジスタを製造するまでの道のりは長いものの、本研究はその先の研究開発を支える方法論を提案したと言えるでしょう。
【論文情報】
| 雑誌名 | : | CrystEnggComm 2019年4月4日 オンライン掲載 |
|---|---|---|
| 論文タイトル | : | Single crystal growth of bulk InGaZnO4 and analysis of its intrinsic transport properties |
| 著者 | : | Yusuke Tanaka(a), Kazuhiro Wada(a), Yuki Kobayashi(a), Takenori Fujii(b), Saleem J. Denholme(a), Ryotaro Sekine(a), Naoki Kase(a), Noboru Kimizuka(c) and Nobuaki Miyakawa(a) |
| 所属 | : | (a) Department of Applied Physics, Tokyo University of Science, Japan (b) Cryogenic Research Center, University of Tokyo, Japan (c) Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, Universidad de Sonora, Mexico |
| DOI | : | http://doi.org/10.1039/c9ce00007k |
宮川研究室
研究室のページ:https://www.rs.tus.ac.jp/miyalab/
宮川教授のページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?122f
東京理科大学について
東京理科大学:https://www.tus.ac.jp/
ABOUT:https://www.tus.ac.jp/info/index.html#houjin
関連記事
-

2019.08.08
本学教員がAsia Pacific Society for Materials Researchにおいて貢献賞を受賞
本学教員がAsia Pacific Society for Materials Researchにおいて、Asia Pacific Society for Materials Research 貢献賞を受賞しました。 受賞者 : 理学部第一…
-
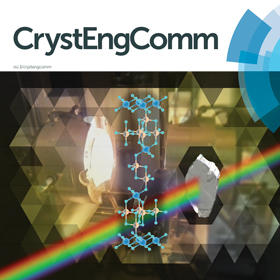
2019.06.03
本学教員らの学術論文が、英国王立化学会発行CrystEngComm誌のHOT Articleとして選出
本学理学部第一部 応用物理学科 宮川 宣明教授らの学術論文が、CrystEngCommで発表された研究のトップ10%と認められたため、英国王立化学会発行CrystEngComm誌のHOT Articleとして選出されました。 なお、大型透明…
-
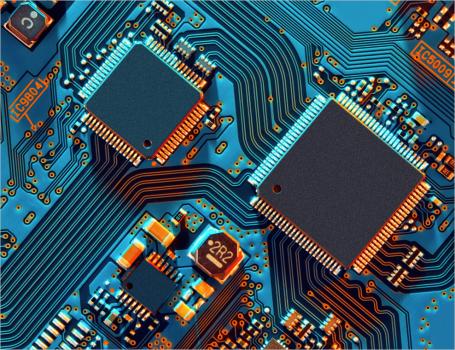
2025.04.28
全結合型イジングマシンLSIシステム、容量と精度のデュアルスケーラブル化に成功
~社会のあらゆる組合せ最適化問題に挑む~研究の要旨とポイント クラウドと異なり、エッジ環境では電力や設置形態に制約があるため、問題の特性に応じて容量(スピン数)と精度(相互作用ビット幅)を最適化することが重要です。 今回、容量と精度の両方向に展開できる画期的なデュアルスケーラブル…
