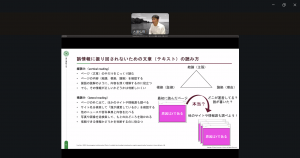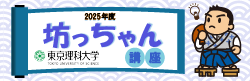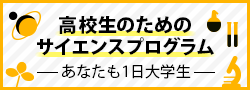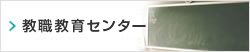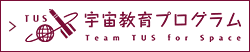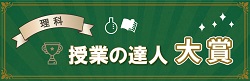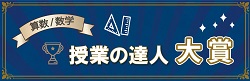2025年度第6回坊っちゃん講座「ネットの情報、どれが本当?ー中高生のための情報リテラシー」開催報告
9月13日(土)に2025年度第6回坊っちゃん講座をオンラインで開催し、100名を超える参加者がありました。
本講座は最先端の研究や応用研究において世界をリードしている研究者が研究の面白さを高校生、中学生および大学生に伝え、勉学意欲の向上と進路選択に資するために開講しています。
今回は、教育支援機構 教職教育センター 大浦 弘樹 教授に講演いただきました。
先生の専門である「教育工学」とは、教育改善のための理論、方法、環境設定に関する研究開発を行い、実践に貢献する学際的な研究領域であり、教育の効果あるいは効率を高めるためのさまざまな工夫を具体的に実践し、成果を上げる技術を開発し体系化する学びであります。(教育工学の創始者の一人、坂元 昂・東京工業大学名誉教授が2000年に発表)
大浦先生は、2026年4月より新設される「理学部第一部 科学コミュニケーション学科」所属となります。新学科の特徴として、デジタル社会に必要となる人材を輩出するため、正確な科学的知識を持ち,科学と社会、科学と人間の生活をつなぎ、課題解決の糸口を見つける手助けをする人材を育成することを掲げています。
※理学部第一部 科学コミュニケーション学科HP ⇒ https://dept.tus.ac.jp/dsc/
続いて講演では、「なぜ人は誤情報を信じてしまうのか?」と題して、専門用語を交えて解説されました。
*フィルターバブル(filter bubble)
検索エンジンやソーシャル・メディアなどで、協調フィルタリングなどのアルゴリズム(仕組み)
によって、ユーザの過去の履歴に沿って表示される情報が自動的に最適化された結果、ユーザー
ごとに(それぞれが好む情報ばかりが見に入る)情報空間ができてしまう現象
*協調フィルタリング
あなたと似た好みの人が好きなものを、あなたにもオススメするためのアルゴリズム
裏を返せば,自分の好みとは異なるものはオススメされにくい(表示されにくい)
*エコチェンバー(Echo chamber)
ソーシャル・メディアなどで、自分と同じ意見や価値観をもつ人たちの集まりの中で、自分の意見
や価値観に合致する情報が繰り返し共有されることで、自身の信念がより強化される現象
上記から、誤情報に振り回されないための文章(テキスト)の読み方として、横読み(lateral reading)や信頼できる情報源としての科学的知見について説明がありました。
その一方、科学的知見(情報)を根拠にした誤情報として、(特にSNSでは)自身の主張を支持する証拠(根拠)のみを取り上げて正当化する「チェリーピッキング」が横行しています。チェリーピッキング(cherry picking)とは、証拠の全体を代表しない(提示された証拠が、ある事柄のすべてを証明するには不十分である状態)特定の証拠のみを取り上げて自身の主張を正当化するとの説明もありました。
最後に、証拠の全体性(Bodies of Evidence)のため、メタ分析/メタアナリシス(meta-analysis)について、複数の研究結果をまとめて、全体としてどんな傾向があるかを調べる方法や、いろいろな研究で出た結果を統合して、より正確で信頼できる結論を出すことの重要性を話され、講演を締め括りました。
講演後、参加者から届いた多くの質問に大浦先生が1つ1つ丁寧に回答してくださいました。
参加者からは、「情報の見方や考え方をあらためて知ることができた。誤情報に惑わされない対策やSNSの情報の危険性についても知ることができた。」「情報の信頼性について、結局最後は自分自身で判断しなければならないというお話に、一層の注意を払っていこうという意識が芽生えた。」「中高生向けとされていましたが、一般にとっても意義深い内容で、良かったです。」「SNSへの接し方が少しだけ変化しそうです。」などの感想が寄せられました。
<講演の様子>