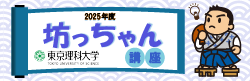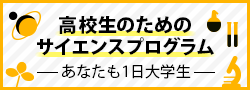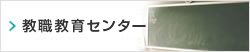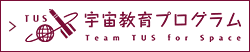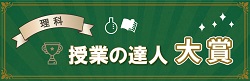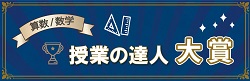科学技術コミュニケーションセミナー「コロナと闘って見えたこと-リスクコミュニケーションの課題」開催報告
今年度の科学技術コミュニケーションセミナーは、元政府コロナウイルス感染症対策分科会会長の尾身茂・結核予防会理事長を招き、「コロナと闘って見えたことーリスクコミュニケーションの課題」のタイトルで6月28日(土)午後2時からオンライン配信で実施しました。135人の参加があり、後半は参加者からの質問を次々と紹介しながら議論が繰り広げられました。前半の2人の演者の講演を含めて約2時間のセミナーでしたが、参加者からは「大変役立ちました」「尾身先生の話は当事者ならではの内容で興味深かった。もっと時間をかけて聞きたかった」「教訓を共有して未来へ伝える必要があると改めて感じました」といった声が寄せられました。
最初に北村春幸・東京理科大学特任副学長が開会挨拶として東京理科大学のコロナ対応について紹介しました。続いて、尾身茂さんが「『1100日間の葛藤』から得た教訓」と題して講演。『1100日間の葛藤』は尾身さんが2023年9月に出した本のタイトルです。
講演ではまず韓国の感染症危機管理センターの写真が紹介され、続いて日本の専門家たちが作業した部屋の写真が映されました。韓国のセンターは、壁の全面に大型ディスプレーがあり、パソコンが整然と並んでいます。まるで映画に出てくるような近代的な設えです。一方、我が国は厚生労働省のあまり広くない会議室で、雑然としたテーブルに人々が横並びに座って仕事をしており、ホワイトボードと壁の張り紙が見えます。彼我の差を強烈に印象づける滑り出しでした。


韓国のオペレーションルーム(西浦博・京都大学教授提供) 日本のオペレーションルーム(専門家会議メンバー提供)
日本の戦略は「社会・経済への影響を最小限、感染防止効果を最大限にしながら死亡者、医療逼迫をなるべく抑える」という「感染抑制」を目指したこと、結果として100万人あたりの死亡者数はほかの先進国と比べて相当低かったこと、一方でGDPの落ち込みは同じぐらいだったことがグラフも使って説明されました。その理由として尾身さんが挙げたのは、①一般市民の協力②政府・自治体:繰り返し行ったハンマー&ダンス③保健医療機関関係者の献身的な努力、の3点です。ハンマー&ダンスとは、感染拡大の際には厳しい制限(=ハンマー)をかけて感染者数の上昇を叩き、落ち着いてきたらそれを緩める「ダンス」期間に入る、という意味です。
さらにオリンピック開催をめぐるやりとりや、専門家が「前のめり」と見られた背景など、具体例を振り返ってリスクコミュニケーションの難しさを語りました。
続いて、堀口逸子・元東京理科大教授による講演「クラスター対策専門家からのSNS発信を担当して」です。リスクコミュニケーションとは何かという基本の解説も入れながら、クラスター対策の専門家から依頼を受けてSNS発信の担当者になったこと、実際にどのようにツイッター(現X)の発信をしていったか、その体験から得られた教訓などを語りました。
休憩をはさんで始まった討論には、内閣感染症危機管理統括庁の池上直樹・内閣参事官も加わりました。この組織は2023年9月に発足し、約1年の議論を経て新しい「政府行動計画」が閣議決定されこと、2025年4月には国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合して国立健康危機管理研究機構(通称JIHS=ジース)ができたことなどが紹介されました。尾身さんは「第一歩として素晴らしいが、本当に機動的にするには乗り越えなければならない課題がいくつかある。どう克服していくか」と質問、池上さんが「一つは訓練をしっかりやっていく。関係者は多岐にわたるので、普段からコミュニケーションを取る。DX(デジタル技術の活用)はすぐには難しいが、着実に進めたい」などと答えました。
司会の高橋真理子・東京理科大学理数教育研究センターアドバイザーがピックアップした参加者からの質問は多岐にわたりました。「ワクチンの効果と副作用」「ワクチンのリスクとベネフィットをどのように伝えたらいいのか」「次のパンデミックのときは国産ワクチンが素早く登場できるのか」「誤情報・陰謀論に対してどのように対処すればいいのか」「統括庁は複雑な組織になっているが、いざというときに素早い決断ができるのか」「コロナ禍ではそれぞれが信じる情報に違いがあり、身内でも理解しあうのが難しかった。異なる考えを持つ人とのコミュニケーションにおいて大切なことは何か」などなど。
尾身さんは「マスクやワクチンの効果は、科学的に調べようとしても限界があり、『誰がみてもこれが正解』というものはない。より正確なものに状況証拠的に近づくことしかできない。だから、それぞれの価値観と立場で情報を選択することになる」と、人によって意見や考えが違うのは当然であることを説明しました。その前提を理解できると、リスクコミュニケーションのあり方も見えてきます。
堀口さんは「発言は自由。それを見て、この人はこういう人なんだなと思ってもらえばいい。それと、SNSは議論する場ではない。ところが、専門家はついつい言いたくなる。専門家も、情報提供とはどういうことか、ちょっと考える必要がある」と指摘しました。
議論を積み重ねるなかで、「相手の感情や価値観を理解しようとすることが大事」「リスクコミュニケーションとは、自分の考えを相手に理解させようとすることではなく、相手の考えや相手がなぜそのように考えるのかを知ろうと対話すること」「誤情報の拡散を防ぐには、その時点での正しい情報を淡々と発信し続けるしかない」「共に創るという共創的コミュニケーションが必要」といった認識が共有されるようになりました。
高橋さんが「国全体での総括も必要だが、それぞれの現場で当事者が議論して教訓を引き出していく取り組みも大事だ」と参加者たちに呼びかけ、最後に眞田克典・東京理科大学理数教育研究センター長が挨拶して終了しました。
※参加者に聞きました。「国の対応について点数をつけるとしたら何点ですか?」
*科学技術コミュニケーションセミナーの様子*


尾身茂・結核予防会 理事長 堀口逸子・東京理科大学 元教授


池上直樹・内閣感染症危機管理統括庁 内閣参事官 高橋真理子・理数教育研究センター アドバイザー(一番右)


北村春幸・東京理科大学 特任副学長 眞田克典・理数教育研究センター長