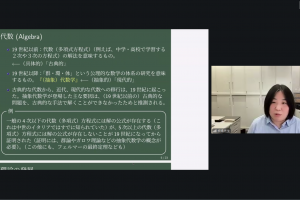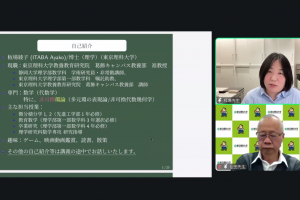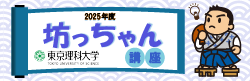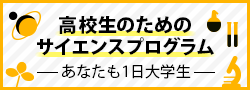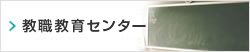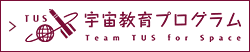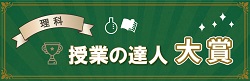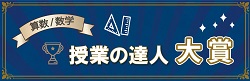2025年度第9回坊っちゃん講座「代数学入門〜環論の世界へようこそ〜」開催報告
11月8日(土)に2025年度第9回坊っちゃん講座をオンラインで開催し、100名を超える参加者がありました。
本講座は最先端の研究や応用研究において世界をリードしている研究者が研究の面白さを高校生、中学生および大学生に伝え、勉学意欲の向上と進路選択に資するために開講しています。
今回は、教養教育研究院 葛飾キャンパス教養部 板場 綾子 准教授に講演いただきました。
冒頭と講演途中に自己紹介があり、東京理科大学における所属や専門、担当授業、趣味のことなどお話しくださいました。
また、とても小さい頃から計算するということに興味を抱いており、幼稚園の年少の頃に計算機とそろばんで大人に計算の原理と仕組みを教えてもらい、自在に使っていたのを覚えているそうです。理系文系問わず好きな科目があった中で、理系の方がものの考え方がシンプルで好きだったこともあり、理系に進学されたことや、小中高の理系の先生方のほとんどが東京理科大学出身者だったことなど、さまざまな理由から東京理科大学に進学されたとお話しされました。
「環論」とは初めて聞く用語だと思いますが、数学の中の代数学の分野の一つです。この講義では、最初に数学的な集まり(=集合)の記法について学習し、大学で習う環の定義を集合の記法を用いて紹介し、その後、数学における環の具体例を見ていこうと思います。大学における厳密な数学の世界の入り口、特に今回は代数学入門として環論の世界を一緒に垣間見てみましょう!と講義概要が示され、講義がスタートしました。
中高生にも理解できそうな参考図書2冊、参考文献3編の紹介があった後、大学の学部で学習する場合の数学の分野として、解析学、幾何学、代数学とあり、代数学の中に線形代数学、(抽象)代数学(群論・環論、体論)、ガロワ理論、整数論、代数幾何学があり、(抽象)代数学の中に環論(可換環論、非可換環論)があると説明されました。
歴史的な話として、代数学(Algebra)は古典的な代数から、近代、現代的な代数への移行が19世紀に起こったことや、環論の発展についてもお話しがありました。
「集合の記法について」として、数学的な対象の集まり(=集合)、元、要素、数の集合の記号、さらに「全称記号、存在記号」についての説明の他、「環(Ring)」の5つの定義、「加法+と乗法×はともに結合法則を満たす」「さらに、加法+は交換法則を満たす」「加法+の逆演算-(減法)はRの中で自由にできる。特に、零元0を持つ」「乗法×の単位元1を持つ」「分配法則が成り立つ」や、可換環、非可換環についても説明があり、環の具体例を多く示しながら、とてもわかりやすく解説してくださいました。
最後に板場先生の研究「多元環の表現論」「非可換代数幾何学」についてのお話しがあり、講演を締めくくられました。
講演後、参加者から届いた多くの質問に板場先生が1つ1つ丁寧に回答してくださいました。
参加者からは、「数学科でどのような研究をしているのかイメージが湧いた」「丁寧に説明していただいたおかげで、大学入学後から抱いていた数学への恐怖心を少し克服できたような気がしました。数学にもっと目を向けたいと思いました。」「とても面白いトピックでした。難しい話をとても分かりやすく具体例を用いながら教えてくださったのでとても満足しています。」「自分自身が現在大学で履修している線形代数に関連する講義を詳しく聞くことができる良い機会になりました。」などの感想が寄せられました。
<講演の様子>