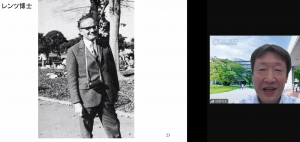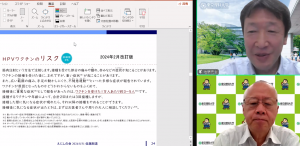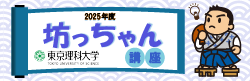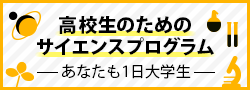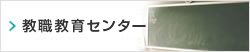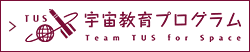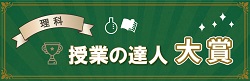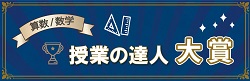2024年度第7回坊っちゃん講座「因果関係とは何か:疫学による医薬品評価の実際」開催報告
10月5日(土)に2024年度第7回坊っちゃん講座をオンラインで開催し、140名を超える参加者がありました。
本講座は最先端の研究や応用研究において世界をリードしている研究者が研究の面白さを高校生、中学生および大学生に伝え、勉学意欲の向上と進路選択に資するために開講しています。
今回は、薬学部 薬学科 佐藤 嗣道 教授に講演いただきました。はじめに自己紹介で、佐藤先生はサリドマイド薬害により手に障害を持って生まれたことや、中学・高校は卓球部に所属し、かなり本気で部活に取り組んでいたこと。その先の進路では文系か理系か迷ったが、分子生物学に興味を持っていたことから理系を選び、北海道大学に進学したこと。2年次の学部選択でも迷った末、薬学部に進んだこと。大学院修士課程は環境科学研究科で疫学を学び、「社会薬学」と出会ったこと。博士課程は東京医科歯科大学医学系研究科にて「薬剤疫学」の研究に携わり、その後、現在まで薬剤疫学研究に従事していることのお話しがありました。
講義では疫学や薬剤疫学の定義について説明された後、1950年代末から60年代初めに世界40ヵ国以上で販売された、鎮静・睡眠薬「サリドマイド」による薬害事件についての説明がありました。厚生労働省から「薬害を学ぼう」のリーフレット(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakugai/)が全国の中学校、高校に配布されていることの紹介もありました。
過敏期と呼ばれる妊娠初期に、サリドマイド1回1錠の服用でも確実に障害が起こります。胎児が2㎜から1㎝にも満たないような時期に、どのタイミングで服用するかでどのような障害が出るのか、ドイツのデータを用いて説明がなされました。
ただ、奇形の原因が最初からサリドマイドだと判明していたわけではありません。ドイツの人類遺伝学者であるレンツ博士が、「遺伝ではこんなに大人数の奇形児が生まれることは考えられない。何らかの科学物質が原因ではないか。」と考え調査を開始し、症例対照研究を基に「レンツ警告」を発しました。これを受けて西ドイツでは直ちにサリドマイドを市場から回収することを決定しましたが、日本では諸外国から遅れること10ヶ月、サリドマイドの販売停止、回収を発表しますが、回収は不徹底であり被害が倍増していくこととなりました。
続けて、「因果関係とは何か」と題し、元東京理科大学教授 増山元三郎氏の著書「サリドマイド」に書かれた「科学者の証言」の紹介、解説がありました。さらに、「因果関係」とは「原因と結果の関係」ですが、「原因とは?」について考えるため、著書「ロスマンの疫学」(KENNETH J.ROTHMAN(著))に書かれた内容が紹介され、その解説がなされました。
最後に「疫学の手法を用いた医薬的評価」として、薬の効果を調べる方法やコロナワクチンを例に臨床試験の方法や発症予防効果の考え方、また、副作用の評価についての解説がありました。
ご講演後、参加者から届いた多くの質問に佐藤先生が1つ1つ丁寧に回答してくださいました。
参加者からは、「東京理科大学に憧れていて、初めて参加しました。興味のある分野の講義が聞けて、とても為になりましたし、受験に対するモチベーションもあがりました。入学して、本物の講義を沢山受け学びたいです。」「先生ご自身の体験を交え講義いただき、薬害問題について、知るきっかけとなりました。また、薬の興味がより深まりました。」「ご自身の経験を元に進む道を選ばれていることに感銘を受けました。私も自分の経験(大きなものはありませんが)を活かせる進学先を見つけたいと思いました。」などの感想が寄せられました。
講演の様子