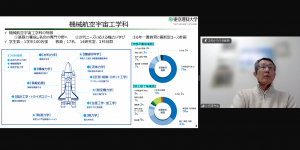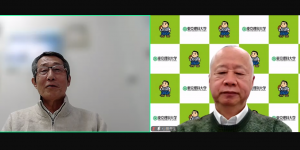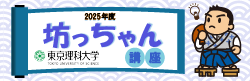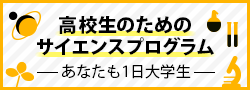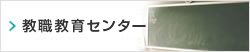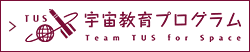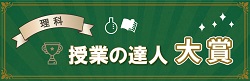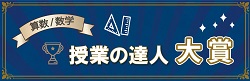2024年度第10回坊っちゃん講座「流れ星はなぜ光る?:高速飛行のおはなし」開催報告
12月21日(土)に2024年度第10回坊っちゃん講座をオンラインで開催し、120名を超える参加者がありました。
本講座は最先端の研究や応用研究において世界をリードしている研究者が研究の面白さを高校生、中学生および大学生に伝え、勉学意欲の向上と進路選択に資するために開講しています。
今回は、創域理工学部 機械航空宇宙工学科 小笠原 宏 教授に講演いただきました。
はじめに「ロケットについて」として、「ロケットの一生 ~誕生からミッション完了まで~」と題した壮大な内容の動画を紹介されました。その後、「宇宙はどこから?→高度100㎞から上が宇宙」であり、空を見上げれば100㎞から上が見えているので、みんな当たり前に宇宙を見ていますとお話しがあった他、ロケットは地球から宇宙にモノを運ぶロボットであること、衛星の軌道、ロケットの速度と重力の関係、ロケットが飛ぶ原理、飛行機との違い等について、とてもわかりやすく解説されました。
続いて「流れ星はなぜ光る?」です。流れ星の正体はスペースシャトルであり、宇宙ステーションから帰還するスペースシャトルが光りながら降りていく様子であることの説明がなされました。
「近づきつつある宇宙旅行」では、民間宇宙旅行は2021年くらいから始まり、現在ではサブオービタル飛行、オービタル飛行の2種類の宇宙旅行がありますが、とても高額であること。今後、一般人が高速飛行(スペースプレーン)を行うようになったり、民間宇宙輸送の実現が近づいていたりすることの解説もありました。
小笠原先生が大学で「研究していること」として、一般人が宇宙旅行に行くためには劇的なコストダウンが必須であり、そのためには現在使い捨てとなっているロケットを完全に再使用できるロケットにする必要があると考えます。その様々な研究概要について、難しい説明は省き、小中学生にも分かりやすいよう解説いただきました。
「私が宇宙にはまった理由」の章では、小笠原先生が小学6年生の卒業文集に「自作の光子ロケットにのって金星へいく」と書いたことのお話しがあり、光子ロケットの解説もなされました。当時の小笠原少年がそこまで宇宙やロケットにはまった理由は、小学校の学級文庫で読んだSFの本であったこと。その後アポロ12号が月面の目標地点に正確に降り立った様子を見た小笠原少年は、学級文庫の本で読んだ内容とリンクして感動し、そこから宇宙にはまっていったそうです。進学した大学には宇宙学科がなかったため航空学科に入り、宇宙の勉強もしたこと。就職した頃はまだパソコンがなかったので手書きで設計図を作っていたこと。これまで様々な設計を行ってきたことや国際共同宇宙探査作戦会議のこと等のお話しがありました。
最後に小笠原先生から「皆さんへのお願い」として2つ。「自分は何が好きなのか?」を見つけて欲しい。先生ご自身も宇宙やロケット、大学の仕事で大変なこと、嫌なこともたくさんあるけれど、好きであれば頑張れます。ぜひ好きなことを探して欲しいと思いますとおっしゃっていました。
また、「なんでだろうを大切に」。普段から「何で?」と思うことを癖にしていると、自分で知らないことを調べ、知識が増えていきます。知らないことは恥ではなくチャンスです。ぜひ普段から「何で?」と思う気持ちを大切にしてくださいと熱いメッセージを送り、講演を締めくくりました。
ご講演後、参加者から届いた多くの質問に小笠原先生が1つ1つ丁寧に回答してくださいました。
参加者からは、「宇宙のことはニュースで見るぐらいであまり知らなかったのですが、スペースシャトルや気圧の話などがとても面白かったです。」「宇宙ステーションの構造や、日本の打ち上げ技術を学べて楽しかったです。」「大学での研究が単なる学問としてだけではなく、航空宇宙工学を通じて実際の社会活動に直接貢献できることがわかりました。」「最初のビデオでロケットが三菱重工から種子島宇宙センターに運ばれるまでの様子を見て壮大さにとても驚きました。普段発射場からロケットが発射される映像ばかり見ることが多いですが、そこに至るまでには多くの研究者やエンジニア、運搬や組み立てに携わる人々の力があってあの映像が成り立つものなのだと改めて実感しました。本日はとても有益で興味深いお話を伺うことができたので、自分なりに深堀して学びを進めていきたいです。」などの感想が寄せられました。
講演の様子