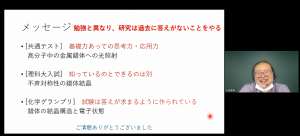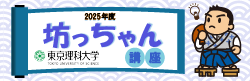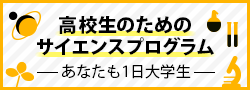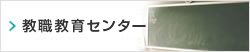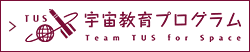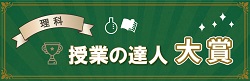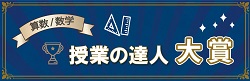2022年度第2回坊っちゃん講座「化学受験術指南~教授が読み解くメッセージ」開催報告
5月14日(土)に坊っちゃん講座をオンラインで開催し、250名近くの参加がありました。
本講座は最先端の研究や応用研究において世界をリードしている研究者が研究の面白さを高校生、中学生および大学生に伝え、勉学意欲の向上と進路選択に資するために開講しております。
講演は、先生の自己紹介から始まり、[共通テスト(2021年1月⼤学⼊学共通テスト)]の「高分子中の金属錯体への光照射」の問題を取り上げ、一見難しそうな問題であるが、高校までの学習で解けるように作られていると説明がありました。実際には、光分解反応の量的関係を問われる物質量(mol)の問題で、見慣れない対象を組み合わせて作られた問題に適用できるか、思考力を問う問題だと説明がありました。
また、入試問題の元ネタになった研究を実験してみた学生の話や秋津研究室で取り組んでいる研究の紹介もありました。
更に、[化学グランプリ]の問題を取り上げ、大学院入試レベルでもおかしくない問題が出てくるとお話があり、問題になった元ネタの研究紹介をした後に、問題についてくる「誘導」を見直すと大学化学への良い橋渡しになると説明がありました。試験は答えが求まるように作られているが、研究は高校までの勉強と違って、過去に答えがないことをやる。過去にとらわれないことにチャレンジできる素養のある人を大学は選ぶための入試をしていると思うと講演を締めくくりました。
その後、参加者から「Q&A機能」を用いて質問を受け、30件近い質問を1つ1つ丁寧に、時間を延長し回答してくれました。
講演の内容に対する質問だけでなく、中学生から「元素記号を覚えられません。覚えるコツはありますか?」と質問があり、「私も周期表全部は暗記していません。使う元素は覚えられるので大丈夫です。」と回答がありました。
また、高校教員から「文系志望の生徒でmolの計算に苦手意識を持ってしまうケースがよく見られます。ハードルを下げる方法等ありますか」と質問があり、「1ダース、2ダースと同じように、12個あったら1ダース。同じように6.0×1023あったら1molで…と数をまとめる単位だと考えればいい」と説明がありました。
参加者からは、「理科の世界にはまだ知らない反応、物質が沢山あるということを改めて感じ、理科をもっと学びたいという思いが更に強くなりました。知らない単語もたくさん出てきましたが、とても楽しい講義でした。」、「秋津先生のお話や説明はとても丁寧で分かりやすかったですが、私には内容が難しかったです。でも理科とは化学と生物と物理がつながっていることを知りました。全てに興味を持って勉強することがそれぞれをよく知る理解する方法かなと感じました。」、「ペーパーテストが解けることと実際に実験ができるかは別であることに改めて気づきました。また、化学グランプリがあることを知り、高みを目指すことを忘れずに勉強していきたいと思いました。」などの感想が寄せられました。
オンライン講座の様子