
 セレクション戦争と文学 8 オキナワ 終わらぬ戦争集英社文庫2020
セレクション戦争と文学 8 オキナワ 終わらぬ戦争集英社文庫2020ガーナの初代大統領クワメ・ンクルマはかつて、支配者は植民地統治が終焉した後、カクテル・パーティを通じて支配を継続すると喝破した。戦後沖縄を代表する作家、大城立裕はその名も「カクテル・パーティ」と題された作品で、軍人や軍関係者の会話を通じて彼らの日常の変容を描く。日中戦争、東アジア冷戦、ペリー来航まで重ね合わせつつ、現在の日米沖縄の関係を問い続ける。日米同盟下、沖縄に米軍基地の大半が置かれる現在も「わたしたち」のあり方を問い続ける不気味な傑作。
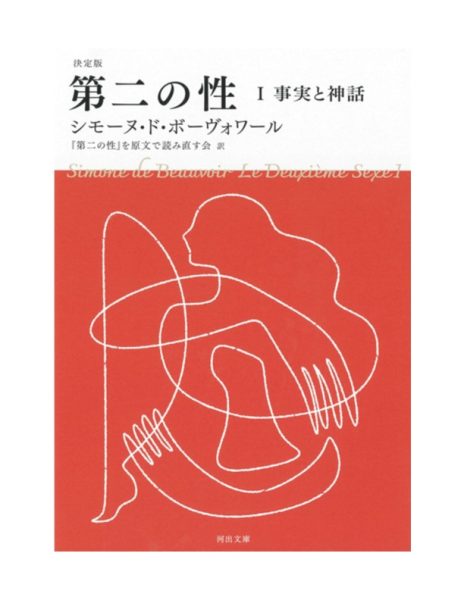 決定版 第二の性I 事実と神話河出文庫2023
決定版 第二の性I 事実と神話河出文庫2023ボーヴォワールの代表作『第二の性』はフェミニズム思想の古典。フェミニズムのみならず、様々な文学者や政治家、思想家の言葉に影響を与え続けている。その手法は、哲学的な問いと文学作品からの引用を組み合わせて、過去の傑作とされる作品を批判的に読み解くところにある。逆に考えると、文学作品を批判的に読み解く作業が、二十世紀半ば以後の女性たちにとって、みずからの生を獲得する作業と不可分であったとも言うことができる。論破というゲームによって他者の言葉に耳を塞ぐことが恒常的に卓越的な行為とみなされつつある現在、そのような退廃的行為とは対極にある批判的読解とは何かを確認するためにも、何度も立ち戻るべき書物。
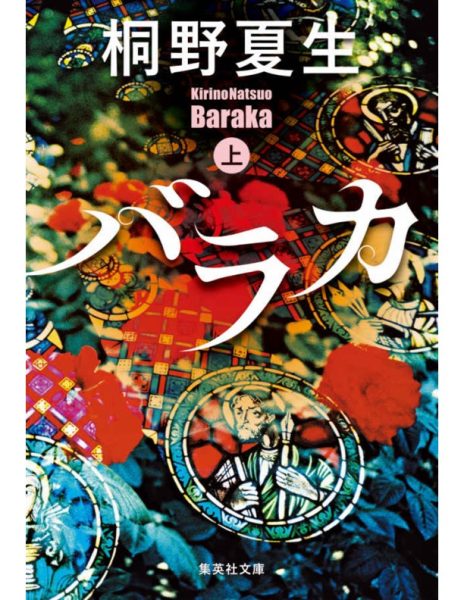 バラカ(上・下)集英社文庫2019
バラカ(上・下)集英社文庫2019本書のモチーフは2011年の東日本大震災である。その後の荒廃した非現実的な日常を、日本社会で民族的マイノリティであり女性である主人公がいかに生き抜くかというところに焦点が置かれている点で、いわゆる震災文学と呼ばれる作品群の中でも特異な位置にある。同時に、本書が証言するのは、ここで描かれる嘘のような、非現実的な日常が、当時のわたしたちにとっては紛れもない現実であったということだ。本作を貫く圧倒的な物語の熱量に身を委ねることはさして難しくもないとはいえ、ここで描かれる「醜悪な」現実の延長線上にわたしたちの現在があることを認めることは容易ではないかもしれない。わたしたち自身の醜悪さに直面することになるからだ。でも、そのように警鐘を鳴らすことが文学の役割でもある。
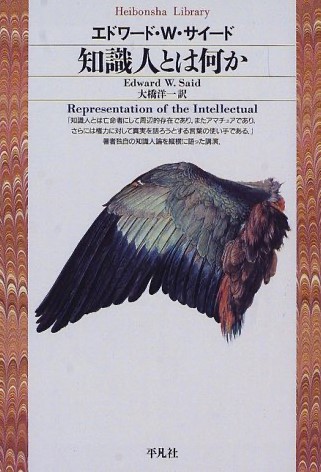 知識人とは何か平凡社ライブラリー1998年
知識人とは何か平凡社ライブラリー1998年サイードなら『オリエンタリズム』が代表作ではあるが、まずはこちらを。イラク戦争の真っ只中の二〇〇三年から〇四年頃のこと。9.11の同時多発テロ事件後、まさかアメリカがアフガニスタンに報復し、イラクにまで攻め込むなんて、と思っていた私はナイーブでした。中東と西洋の「対立」についての先入観を180度変えてくれたサイードの入門書とでもいうべき本書は、すでにホコリにまみれて久しい知識人なる言葉を磨き直し、魅力的な存在として差し出した。言葉を蘇らせることも、学者や作家の大事な仕事。野球選手よりも、サッカー選手よりも、知識人はカッコいい。
 方法序説岩波文庫1997年
方法序説岩波文庫1997年高校生の時、同級生の父親の葬儀に行った。いつもはひょうきんな彼が、顔をクシャクシャにして泣いていたこと、今でも時々おもいだす。それからしばらくして、何の前振りもなしに差し出したのがこの本だった。もちろん通して読んだ。よくわからなかったものの、考えることの困難をかろうじて理解することができたように思う。それ以後、哲学への憧れが芽生えたが、いまだにちゃんと哲学に取り組めてない後ろめたさがのこる。
 カフカ短編集岩波文庫1987年
カフカ短編集岩波文庫1987年就職氷河期の九十年代末、文学部という将来の見込みが全くないところに迷い込み、何かになりたいものの何になりたいか分からず、ぼーっと時間ばかり過ぎていく日々。そんな中、翻訳家の先生が教える授業で精読した。ほかにも武田泰淳や深沢七郎、フラナリー・オコナーなどをじっくり読み、引用し、解釈することの楽しさを初めて知った。同じカフカなら『変身』も捨てがたいが、「掟の門」「流刑地にて」をはじめ、この短編集に収められた作品の破壊力は一度味わったら忘れられない。当時、おなじグループで発表した学生は「自分は自己啓発本しか読まない」と豪語していた。文学と縁遠いと思っている人こそ読むべし。意味を求めてはいけない。不思議と気持ちが軽くなり、笑いがこみ上げてくる。
 アンダーグラウンド講談社文庫1999年(単行本の初版は1997年)
アンダーグラウンド講談社文庫1999年(単行本の初版は1997年)理科大生全員必読。なぜ理系のエリート集団が説明不可能なほどの悪に邁進してしまうのか。一九九五年三月の地下鉄サリン事件で一変した世界を被害者の視点からインタビューで説き起こしたノンフィクション。続編は加害者へのインタビュー本『約束された場所で』。社会にかかわることはどういうことなのか、考えさせてくれる。森達也監督のドキュメンタリー映画『A』『A2』も併せて必見。
 親指Pの修業時代、上・下河出文庫2006年(単行本初版は1993年)
親指Pの修業時代、上・下河出文庫2006年(単行本初版は1993年)欲望のあり方を相対化するという意味においてニーチェ主義者である著者は、稀代のスタイリストとして評価が高い。だが、本書を通読して分かるように、物語の語り手としても稀有である。「男らしさ」「女らしさ」(はたまた「日本人らしさ」「〜人らしさ」)のようなものが何の根拠もない薄っぺらな物語に支えられているはずなのだけれど、自らが囚われていることに最も気づきにくいことも確か。なぜなら、身体性の一部になってしまっているから。このロジックをひっくり返し、著者は女性主人公の足の親指にペニスが生えてくるという設定を発明した。ゲーテ先生もびっくり、世の中が裏返って見える永遠の教養小説。
