
- どうか皆さん、最近、似たような行為が私たちにあったのではないか、いや、似たような行為はなかったのではないかと、心のなかをじっくりさぐって頂きたい。
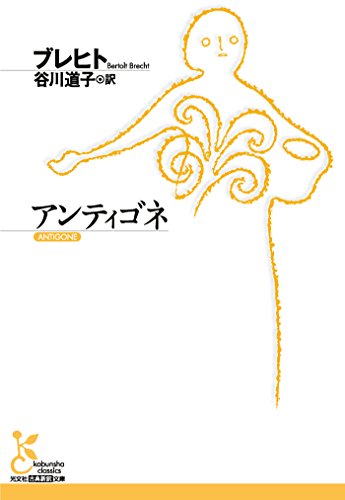 アンティゴネ光文社2015年
アンティゴネ光文社2015年はるか昔のテーバイで、二人の王子が王位をめぐって殺し合った。摂政のクレオンは、国を守って死んだ王子は埋葬するが、攻め込んだ王子の遺体は野晒しにせよ、悲しむことも禁ずるというお触れを出す。王子たちの妹アンティゴネは、野晒しにされた兄に土をかけて弔い、法を犯したかどで生きたまま岩牢に幽閉される。
三大悲劇詩人の一人ソフォクレスのギリシア悲劇『アンティゴネ』は、何世紀もの間読み継がれ、翻訳され、上演され、法と正義、国と家族、生と死、権力への抵抗などさまざまな観点から解釈されてきた。20世紀ドイツの劇作家ブレヒトによる改作版は、独特の意表を突く言い回しが光る。 - どんなに危険だって、やらなきゃならない物事があるんだよ。…そうしなければ、もう人間じゃなくて、けちなごみくずになってしまうからだよ。
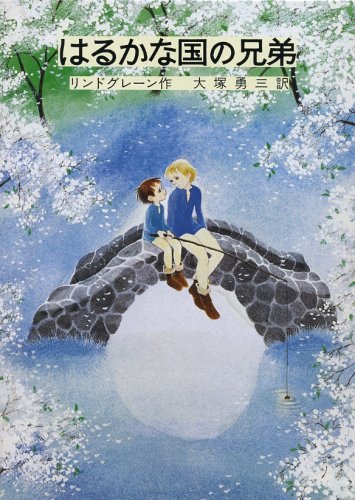 はるかな国の兄弟岩波書店1976年
はるかな国の兄弟岩波書店1976年地上での生を終えた10歳の少年クッキーは、13歳の兄ヨナタン・レヨンイェッタが待つ死後の世界ナンギヤラに転生する。「たき火とおはなしの時代」での胸躍る冒険を望んだクッキーだが、待ち受けていたのは暴君の圧政と自由を求める戦いという「あってはならない冒険」だった。
美しく、強く、聡明な兄を尊敬し、どこまでもついて行くクッキーは、自分の弱さや臆病さと向かい合い、「レヨンイエッタ」(獅子の心)の名に恥じない勇気をもって、命を懸けた戦いに参加する。『長くつ下のピッピ』の作者が円熟期に書いた名作で、スウェーデンでは生と死を考える本としても名高い。 - 大むかしには、いまわたしたちが見ている太陽や月とは、すっかりちがった、べつの太陽と月がありました。
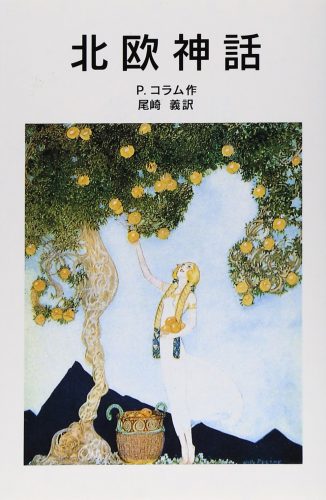 北欧神話岩波書店2001年
北欧神話岩波書店2001年世界を構成する木ユッグドラシルは倒壊の危機にあり、神々は最初の巨人イーミル(ユミル)を殺して世界を創造した時から、生き残った巨人とその子孫に脅かされている。神々の父で死神のオージン(オーディン。Wednesdayの語源)、力強く短気な雷神トール(Thursdayの語源)、戦乙女ヴァルキリア、勇敢な戦神チュール(Tuesdayの語源)、愛と豊穣の女神フレイア(Fridayの語源)、虹の橋の番をする神で人間の祖となったヘイムダル、巨人出身だがオージンの義兄弟として神々の世界に暮らすロキ。巨人族と滅ぼしあう最後の戦い「ラグナロク」に向かう運命の中で、神々が、生き、愛し、知恵を働かせ、戦うさまが個性豊かに描かれる。
日本のゲームや映画、漫画にも多くの題材を提供する北欧神話の神々の物語を分かりやすく書いた一冊。 - 死んでいるのでもなければ、生きているのでもないような自分自身の姿を見る。クラバートの生命を形成しているすべてが、いまはこの外界にあるのだ。からだの外にあるのだ。いまは自由で、かろやかで、なんの拘束も感じない。
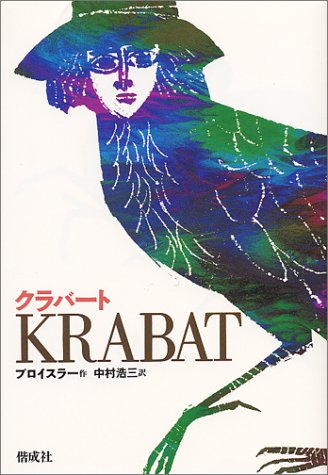 クラバート偕成社1980年
クラバート偕成社1980年物乞いの少年クラバートは、ある新年に夢の中で十一羽のからすに名前を呼ばれ、その夢に導かれて水車小屋の徒弟になる。その水車小屋は、昼間は粉ひきの臼が回るが、金曜日の夜になると親方から魔法を教わる<魔法の学校>だった。井戸を翌日まで封鎖する術、姿を変える術、自分のからだからぬけだしていく術、頭のなかで他人に話しかける術…。少年クラバートの目に便利なものと映った魔法と秘密の多い水車小屋は、時とともに不気味な側面を表していく。
ドイツのスラヴ系少数民族ソルブ(作中では「ヴェンド人」)に伝わる伝説を、『大どろぼうホッツェンプロッツ』の作者がハイティーン向けにリライトしたロングセラー。 - わが食う魚(いお)にも海のものには煩悩のわく。
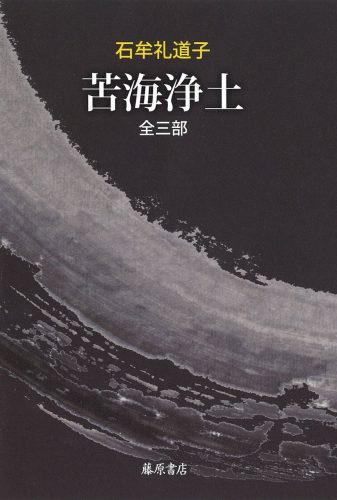 苦海浄土 全三部藤原書店2016年
苦海浄土 全三部藤原書店2016年1960年1月、「奇病」と題する短編作品が九州の雑誌『サークル村』に掲載された。後に水俣病として広く知られることとなる病に罹患した女性の「聞き書き」をもとにした「ルポルタージュ」とされていた。これを皮切りに、石牟礼道子は雑誌『熊本風土記』に「海と空のあいだに」と題する連載を開始、1969年に第一部『苦海浄土 わが水俣病』、1974年に第三部『天の魚』、一連の水俣病訴訟がほぼ終結した2004年に第二部『神々の村』が刊行される。
患者の一人称語りは、患者をたずねる「わたくし」の一人称語り、カルテなどの資料と並ぶ本作の構成要素であるとともに、本作最大の特徴である。この部分は現在、聞き書きをもとにしたルポルタージュではなく、患者が心の中で思っていることを石牟礼が言葉にした文章であることが知られている。過酷な現実の中で患者たちの夢見た前近代と近代を描出し、「苦海」が「浄土」となる瞬間を語る、現代日本文学の最高峰。
