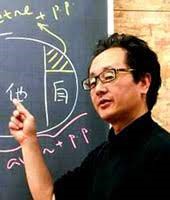
- ひとりになって、音楽を聴くかのように
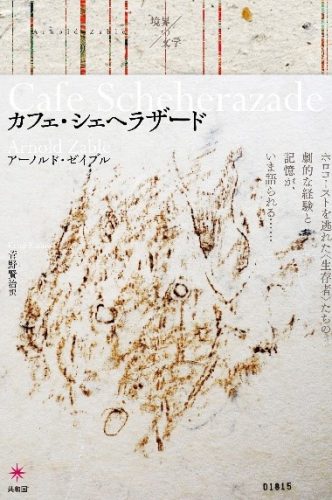 カフェ・シェヘラザード共和国2020年
カフェ・シェヘラザード共和国2020年読みながら、「まるで音楽を聴いているようだ」と感じる本というのが、あると思いませんか? 私は、このオーストラリアの現代作家の代表作を原語で読んで、最初の数ページ目からずっと、そう感じていました。中身はポーランドのユダヤ難民たちの話なのですが(一部、日本の神戸にも関係しています)、この本の主役は「音」だと思う。自分で訳した本を、このような場で「推薦」するのは烏滸がましいとも思ったのですが、訳しながら、「これは理科大生の皆さんにも読んで欲しいなあ」と感じていましたので、あえて選びます。インターネットとSNSの発達により、ついに私たちは、寝ているとき以外、常に誰かと繋がっており、決して「ひとり」になれない時代を生きるようになってしまいました。でも、このコロナ禍で、人と会えない日々が長引くなか、逆に「ひとり」で、ただ一冊の本とともに、じっと過ごす時間の大切さを思い出してみるのはどうでしょう。情報を得るためではなく、ただ音楽を聴くかのように。
- 科学・学術の世界での「性差」を考えてみたいときに
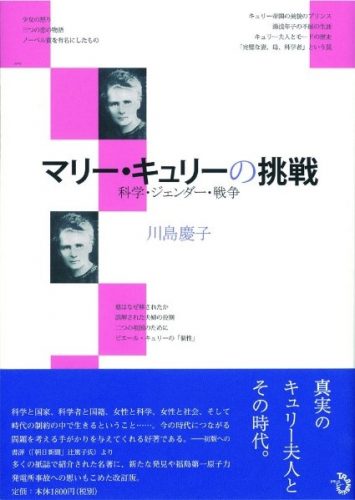 マリー・キュリーの挑戦 科学・ジェンダー・戦争トランスビュー2016年
マリー・キュリーの挑戦 科学・ジェンダー・戦争トランスビュー2016年ネタばれですが、来年度から「科学技術と文化」の授業を「映画に見る科学者の肖像」というテーマでやってやろうと企んでおり、その予習のための参考文献のひとつがこれです。キュリー夫人を題材にした映画には、有名な「キュリー夫人」(1943年、アメリカ)と、本邦未公開の「レディオアクティヴ」(2019年、イギリス)がありますが、これらの映画作品を論じるにあたって、川島さんのこの本は、とても助けになります。同時に、近代(そして現代も)の科学・学術の世界が、いかに男性中心主義によって歪められてきたか(いるか)、深く反省させられます。生理的な条件に関係のない科学、学術、そして大学の世界も、早く、特に「努力目標」などにしなくても、男女半々(もちろんLGBTもそこに含めて)になる日が来るといいなあ、「ジェンダー論」などというものが論じられる必要のないような世界になるといいなあ、と心からそう思います。
- 何だかわからないけど、人生が嫌になったときに
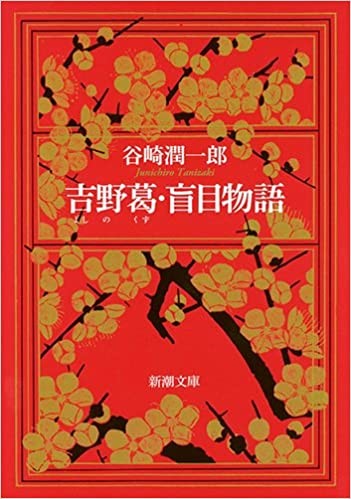 吉野葛新潮文庫、岩波文庫、ほか1931年
吉野葛新潮文庫、岩波文庫、ほか1931年大学院生の頃、人間関係とか進路とかのことで、どうしようもなく落ち込んでしまい(今から考えると何でもないことなのですが)、真面目に自死も考えたことがありました。その時、ふと手にしたのが、この谷崎の隠れた逸品です。読んで、居ても立ってもいられなくなり、奈良の吉野へ一人旅に出たくらいです。秋でした。よほど死にたい顔でもしていたのか、泊まった民宿のおじさん、おばさんから、「あんた、早まるじゃなかよ」と声をかけられたのを覚えています。作中、白狐の「恋しくば尋ね来て見よ和泉なる信太の森のうらみ葛の葉」の歌が、どういうわけか、私に「もうちょっと生きてみよう」という気を起こさせました。その因果関係は、いまもって不明です。おそらく、「まだ、自分の知らない世界がある」と感じたからではないでしょうか。落ち込んだときは、下手に「ストレス解消」「悩み事Q&A」といったハウツー本に手を出すより、文学の〈名著〉を噛むように読むのも捨てたものではないと思います。
