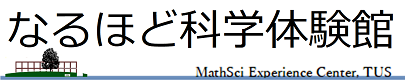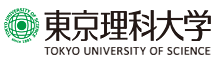インストラクターブログ
持永先生トークイベント
先日、神楽坂キャンパスの近代科学資料館で開催された企画展「京都の3人」にあわせ、持永芳文先生(元東京理科大学理工学部講師・電気学会フェロー)によるトークイベント「京都電気鉄道からLRTまで―難波正の貢献―」が行われました。
講演では、日本初の路面電車である「京都電気鉄道」の誕生と、それに続く京都市電を支えた京都帝国大学教授・難波正の功績について紹介されました。今回の企画展に先立って行った調査で見つかった京都日出新聞の資料によると、難波先生は、祇園祭の山鉾巡行で路面電車の電線が支障になる問題に対し、「巡行時に一時的に架線を外すことで解決」した際に尽力されたということがわかっています。
また、持永先生は、1895年に開業した京都電気鉄道が、琵琶湖疏水の水力を利用した蹴上発電所で生み出した電力で電車を走らせたことを解説されました。電車は“トロリーポール”と呼ばれる棒で架線から電気を受け取りましたが、電流をレールから変電所に戻す仕組みが難しく、大地への漏電や通信線への影響が課題となっていました。そのため京都電気鉄道では、レールのつなぎ目を銅線で結び、さらに地下に帰線を埋めるなど、当時としては先進的な対策が取られていたそうです。
講演の後半では、路面電車の集電装置や電動機駆動方式の変遷を経て、近年注目される低床式車両(LRV)の活用や、軌道・電停の改良による乗降の容易性、定時性、速達性、快適性などの面で優れた特徴を有する軌道系交通システム(LRT)へと続く技術の流れが紹介されました。富山市、熊本市、宇都宮市をはじめとした日本各地において、最新のLRTは静かで環境に優しく、乗降のしやすさにも配慮された交通システムとして進化しています。
京都から始まった路面電車の歴史が、今もなお人々の生活を支えていることを感じられる、学びの多いトークイベントでした。
教室にて