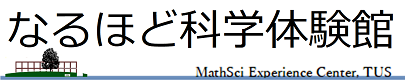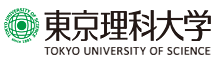インストラクターブログ
数学好き必見!三輪桓一郎先生の論文
こんにちは。学生スタッフのA.S.です。昨年は和田雄治先生の31編にも及ぶ物理学校雑誌へ寄稿された論文の要約をしました。今年は企画展「工学者を育成し、京都の近代化と地域振興に寄与した『京都の3人』難波正・三輪桓一郎・玉名程三」に向けて、三輪桓一郎先生が物理学校雑誌に寄稿された論文の要約を担当しています。三輪先生は数学にまつわる内容で12編書かれています。要約していて感じたことをここにまとめておこうと思います。
まず数学は代数学、解析学、幾何学の三つに大きく分けられます。もちろん明確な境界はなく、相互に関連していますが、近年は各研究分野ごとに深化する傾向にあります。これが近年の数学が発展しない理由の一つだという意見もあります。それはさておき、三輪先生が書いた物理学校雑誌を眺めてみると、『多元一次方程式の解法に付て』、『一つの曲線に關せるアベリヤン積分に就て』、『代数学と幾何学の関係一斑』に代表されるように、数学全般にわたって書かれていることが分かります。まだ現代ほど数学が細分化されていないというのもあると思いますが、全分野において理解を深めることは中々できないことです。現在の大学一年生が習う内容で高校生も理解できるものも多いですが、当時は数学の最先端だったに違いありません。三輪先生が第三回万国数学者会議へ日本代表として出席されたのも納得できます。
三輪先生が寄稿した物理学校雑誌の要約は無事終わり、現在は三輪先生が出席された第三回万国数学者会議の四大講演を解読しています。こちらは各出身の言語(フランス語、英語、イタリア語、ドイツ語)で書かれているので翻訳ツールを使い、ときにはニュアンスを引き継ぐために単語をひとつひとつ調べながら要約を進めています。数学が好きな方にとって、今回の企画展の三輪先生コーナーはかなり必見かもしれません。

企画展準備中