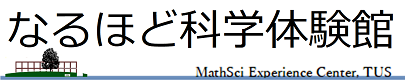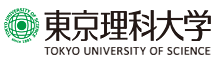インストラクターブログ
生徒のための授業づくり
皆さん、こんにちは。学生スタッフの K.Y です。ブログを書くのは約半年ぶりになります。
私は、大学で教職課程を履修しており、日々、教師としての資質を身につけるため学習に励んでいます。教師には求められることは多岐にわたります。たとえば授業では、「何を学ぶか」、「どのように学ぶか」、「何ができるようになるか」を考える必要があります。他さらに、より理解を深めるために生徒同士の対話をどう取り入れるか、一連の授業をどのように設計していくかも重要です。大学では、こうした力を身につけるために模擬授業を行っています。実際に授業案を作成し、学生同士で授業を実施しています。今回は、この授業の作り方について皆様にご紹介したいと思います。
日本の一般的な授業スタイルといえば、一斉授業です。教師が黒板の前に立ち、一方的に生徒へ授業するスタイルです。しかし、一斉授業では生徒一人ひとりの理解度を把握すしにくく、その個人差に応じた指導をするのが難しいという問題があります。このような問題点を解決すべく、大学で学ぶ授業づくりでは、生徒同士の対話を重要視しています。対話を行うために、グループワークやディスカッションなど、一つの課題に対して複数人で取り組む活動が求められます。こうした活動は私が授業を考えるうえで、必要な要素と考えています。授業案を作成する際、まず生徒がなにを学ぶか明確化します。明確化することで、これから学ぶ内容の見通しを持てます。次に、その学習内容に関連したグループワークを取り入れます。グループワークでは、意見の比較・分析ができるように設計しています。比較を通じて、自分にはなかった視点を知り、分析を通じて、課題の解決策の手がかりを発見することができます。このような過程を経て、生徒自身の発見・学びを得ることを想定しています。最後に、全体のまとめを行います。まとめを行うことで、学習した内容を振り返ることができ、学習内容の定着を図ることができます。
このようにして、私は授業づくりに取り組んでいます。まだ学びの途中ですが、これからもより良い授業をつくれるよう努めていきます。
文部科学省
主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善
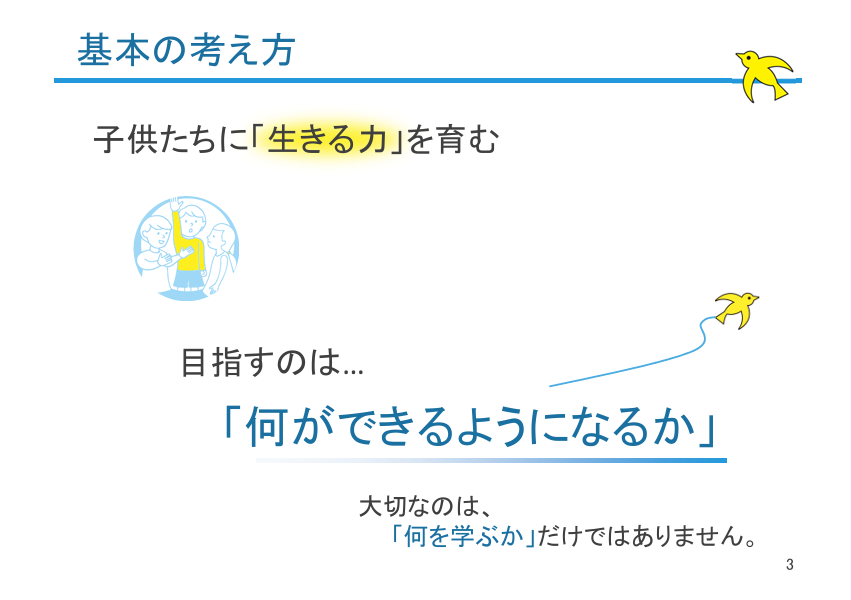
主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善