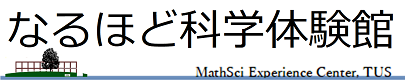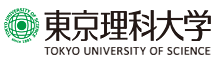インストラクターブログ
マルスラン-ラングロワ
こんにちは。学生スタッフのT.Y.です。現在、秋ごろに近代科学資料館で開催予定の企画展に向けて準備を進めています。今回の企画展で取り上げる人物のひとり、玉名程三は、物理学校雑誌にて「原子運動に就て」という記事を執筆しました。その中で彼は、「ラングロハ」という人物の研究を紹介しています。
私は、この「ラングロハ」とは一体誰なのか、そして玉名はその人物のどの論文を引用していたのかを調査しました。今回は、その調査の過程と方法についてご紹介したいと思います。
調査の手がかりとなったのは、「ラングロハ」という名前と研究内容のみで、彼がどこの国の研究者なのか、どんな論文を執筆したのかも分からない、ほぼ白紙の状態からのスタートでした。まず「ラングロハ」という科学者が実在するかどうかを調べましたが、辞典やデータベースを探しても該当する人物は見つかりません。そこで私は、当時のカタカナ表記には誤写や音の揺れが多いことに着目し、似た音を持つ人名をフランス語やドイツ語の中から一つずつ検討していきました。その過程で、「ラングロハ」は実は「ラングロワ」と読むのではないかという仮説にたどりつきました。「ラングロワ(Langlois)」はフランスで比較的よく見られる姓であり、科学史にも登場する可能性があります。そこで「Langlois」と、フランス語で「原子運動」を意味する「mouvement atomique」を組み合わせて検索したところ、ついに玉名が紹介していた論文を見つけることができました。長い探索の末に行き当たった瞬間は、謎解きの答えにたどりついたような感覚で大きな達成感を感じました。
今回の企画展では、玉名が執筆した「原子運動に就て」の現代語訳を展示しています。 玉名が紹介したラングロワの研究は、現在ではほとんど知られていません。しかし当時に目を向ければ、それはヨーロッパで議論されていた最先端の研究の一つでした。ニュートンやアインシュタインのように現代まで残る理論ばかりでなく、その時代ごとに注目され、熱心に研究された成果があり、玉名はそうした最新の知見をいち早く日本に伝えたのです。
本展示を通じて、玉名が当時の最先端科学を紹介し、日本の科学発展に橋を架けていたことを感じ取っていただければ幸いです。
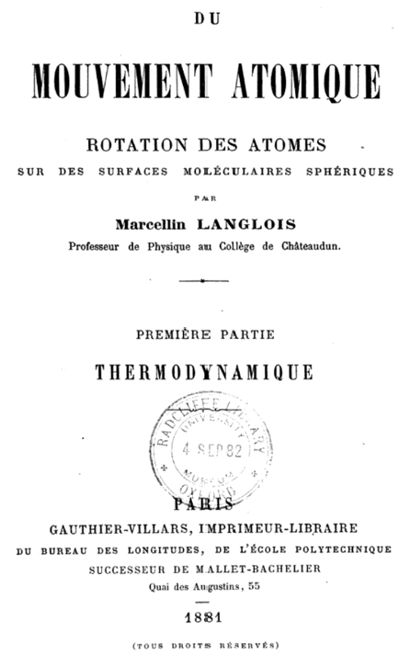
表紙