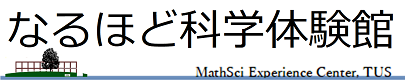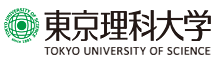インストラクターブログ
戊辰戦争
こんにちは。学生スタッフのT.Y.です。現在、秋ごろに近代科学資料館で行われる企画展の準備をしています。その一環として、1868年から1869年にかけて起きた戊辰戦争について調査しています。戊辰戦争は旧幕府軍と新政府軍(主に薩摩藩や長州藩など)が対立した内戦で、日本の近代化と明治維新への転換点となりました。
今回は主に、戊辰戦争における二本松について調査を進めました。戊辰戦争について調べる前、恥ずかしながら私は、戦いのほとんどが京都や江戸で起きた出来事だと思っていました。しかしながら、この戦争は新政府軍が江戸城を無血開城したのち、旧幕府軍に属する二本松藩や仙台藩、会津藩などの東北諸藩をせん滅すべく、東北地方へと北上したのです。新政府軍と東北諸藩との戦いには「白虎隊」や「二本松少年隊」など、13歳から17歳の少年隊士も参戦し、多く命を落とした悲惨なものだったと言われています。また、戦後の敗戦藩への扱いも厳しいもので、領地の削減や家臣の処分が行われたとされています。このような背景から、現在でも長州や会津の間には戊辰戦争による遺恨が残っていると言われています。
今回の二本松における戊辰戦争調査のきっかけは、東京理科大学の前身である東京物理学講習所(1881年設立)の設立者21名のうちの2人である、中村精男・和田雄治がそれぞれ長州・二本松出身であった点にあります。2人は共に気象観測を行うなどの親交があり、日本の気象学発展に大きく貢献しました。戊辰戦争には直接関わっていないものの、敵対の立場であった2人が、このように手を取り合っているのは、「科学」とは非常に面白いものだと改めて思い知らされました。具体的な内容は、ぜひ企画展にお越しいただき、見ていただけたらと思います。

二本松少年隊