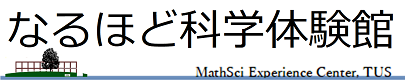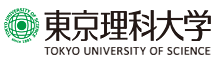インストラクターブログ
100年以上前の氣象集誌
こんにちは。学生スタッフのA.S.です。現在、秋頃に近代科学資料館で行われる企画展の準備をしています。その一環で、100年以上も前の大正7年に刊行された氣象集誌を調査しました。興味深いことがあったので書きたいと思います。
氣象集誌には多くの論文が昔の言葉遣いの日本語で書かれていました。私が今回探していたのは、和田雄治の没後に刊行された「和田雄治の略伝」でした。具体的な内容は企画展にお越しいただいて是非ご自身で見ていただけたらと思います。氣象集誌の構成が分からずに地道に探して、ようやく和田雄治の略伝を見つけました。ですが、なんとエスペラント語で書かれていたのです。私はエスペラント語を知らなかったので大変驚きました。エスペラント語はいわゆる人工言語というものらしいです。1887年頃に母語が異なる人同士のコミュニケーションを簡単にするために作られたのだそうです。特に少数民族の言語において活躍するのだと思います。辞書を引きながらエスペラント語を解読し、氣象集誌の調査は無事に終わりました。解読している過程で、英語の雰囲気をどこかに感じ、意味が分かる単語もありました。例えば、エスペラント語の“observatorion”は英語の“observe”から予想できるように観測というニュアンスがあります。エスペラント語の成り立ちが非常に興味深いですね。
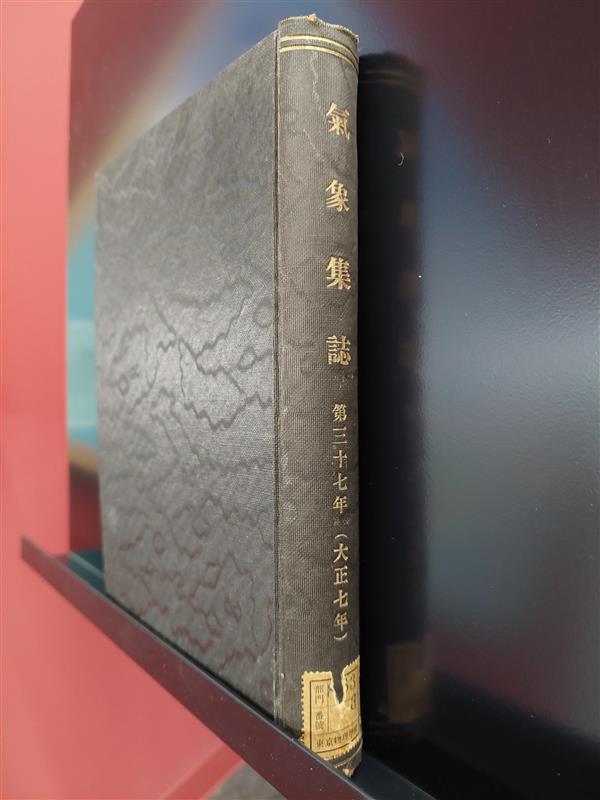
氣象集誌 第37年(大正7年)