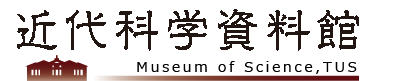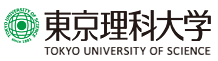資料館スタッフブログ
ゼミ選択と解析学
こんにちは、資料館学生スタッフのS.H.です。私は数学科なのですが、数学科は三年次に数学研究というものを受講することになっています。これは、輪読形式(同じ本を何人かローテーションで発表する方法)で本を進めたり、研究発表をしたりするものです。数学研究はA〜Fに分かれていて、おおよそ、代数学、幾何学、解析学がそれぞれ2つからなり、それらの一つを選んで受講します。私は、悩んだのですが、解析学の分野を受講しようと考えています。今回は、解析学がどのような分野で、私がどういう変遷でなぜ解析学を選ぼうと思ったのかを話したいと思います。
まず、解析学とはどういう分野なのでしょうか?これには明確な答えはありませんが、私が好きな表現として、極限を用いる分野、という解釈があります。解析学の大きな一部分として微分積分学が挙げられますが、これには極限という概念が必要不可欠です。また、解析学の祖として、アルキメデスの名が挙げられることがありますが、彼もまた極限的な操作を用いて、面積を求めることをしていました。
ここである一つの疑問(これは私が解析学に興味を持った理由の一つでもある重要なものでもあります)、極限とは何か、というものが浮かびます。我々は無限の操作を行うことはできません。それなのに、解析学は極限というものを扱い、対象の性質を分析します。ここにギャップを感じませんか?そして、どのようにその問題を解決したのかが気になりませんか?
実は、極限というものが数学的に定式化され、厳密な定義を与えられるには多大な時間を要しました。17世紀、微分積分学を大きく発展させたニュートンやライプニッツですら、極限の厳密な定義には立ち入っていません。というよりも、その時代の人々にとって、関数というものすら現代ほど厳密に定義されておらず、極限を厳密に定義するという発想に至らなかったのだと思います。ただ、解析学が研究され、級数の概念や、連続性、微分可能性の概念が生まれてくると、どのようなときに級数展開可能なのか、極限の操作が成り立つのか、という意味で、極限に対する理解が必要になりました。それらはコーシーによって推し進められ、ワイエルシュトラスによって、19世紀後半に、現代でも知られる極限の定義、イプシロン-デルタ論法が確立されます。このイプシロン-デルタ論法は多くの現代的な微分積分学の教科書に載っていて、私も学んだのですが、極限というイメージ的には無限の操作を、有限の数式で書き下すというその定義に感服したのを覚えています。この極限の定義が、私が解析学に惹かれた理由の一つです。
これは、解析学以外にも感じられることなのですが、数学の定義を見ると綺麗や上手い、といった感情になる時があります。自然数や整数、有理数、そして実数の定義、曲面の定義や、積分の定義(これも私が解析学が好きになった理由の一つです!)、そういったものを調べてみるとより数学の面白さに触れられるかもしれません。

好きな数学書