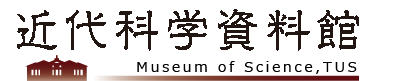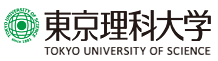資料館スタッフブログ
第三回万国数学者会議の要約
こんにちは。学生スタッフのA.S.です。10/1~12/12の間、近代科学資料館で「工学者を育成し、京都の近代化と地域振興に寄与した『京都の3人』難波正・三輪桓一郎・玉名程三」が行われています。私が担当していた第三回万国数学者会議の四大講演の解読が無事終わりました。第三回万国数学者会議は三輪桓一郎先生が出席され、物理学校雑誌でも『第三囘萬國数學者大會景況』を寄稿されています。
四大講演は『第三囘萬國数學者大會景況』の最後に紹介されています。バンルベル氏の『微分方程式の積分法における最近問題について』、グリーンヒル氏の『歴史上より見たる独楽の数学的理論』、セーグル氏の『今日の幾何学と解析との関係』、ヴィルチンゲル氏の『リーマンの双曲線幾何の級数について』の四大講演を解読してきました。こちらは各出身の言語(フランス語、英語、イタリア語、ドイツ語)で書かれていて、ニュアンスを汲み取るのがとても大変でした。解読してきた感想として、数学的に楽しめたのはバンルベル氏、面白かったのはグリーンヒル氏、体系的なつながりを感じられたのはセーグル氏、リーマンの歴史を知れたのはヴィルチンゲル氏の講演でした。
四人目のヴィルチンゲル氏の文章が一番長かったのですが、和田雄治先生の経験もあって長さには慣れました。しかし絶望してしまった瞬間がありました。毎回一枚のポスターに要約するのですが、内容の解読が半分までようやく行ったころ、ポスターでは既に字数があふれていました。つまり今の字数を半分ほど削って残りの解読を上手く入れなければいけないということですね。別にこれはいいんです、今までと同じ作業ですから。問題は次の文章でした。「ここまでの余談のあと、本題に戻り~」……え?目を丸くしました。私がここまで頑張って入力して削ってきた内容は余談だったのです。ここから本題が始まるという事実を受け止めきれず、私はなるほど科学体験館の中を散歩し始めました。
紆余曲折あって無事に現在、四大講演が全て展示されています。三輪先生の物理学校雑誌ともあわせて、是非是非努力の結晶をご覧ください。
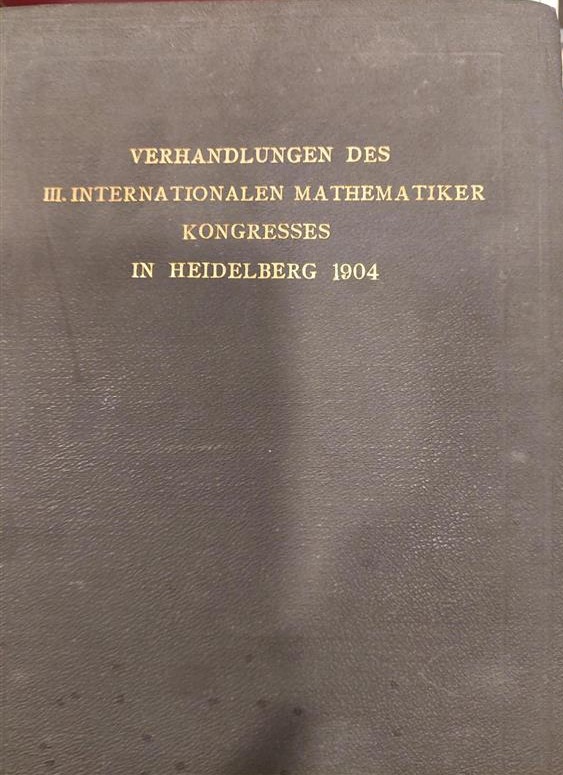
第三回国際数学会議の議事録