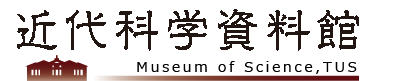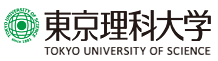資料館スタッフブログ
八卦と占いについて
こんにちは、学生スタッフのK.K.です。今日は八卦(はっけ)を用いた占いをご紹介します。
八卦とは中国の古代思想である易学(えきがく)において自然現象や人間社会のあらゆる事象を表現するのに用いられる記号体系のことです。簡単に言うと三つの線を組み合わせて作られた記号のことで、線は陰と陽という2種類の線があるので8通りの記号があるというわけです。
占いは遙か昔から様々な場所で行われてきました。そのため、占いの方法には様々な種類があります。そして、易学においても易占と呼ばれる占いの方法があります。今回は易占の一種である略筮法による占いを簡単に紹介します。
略筮法(りゃくぜいほう)では筮竹という50本の棒を使って占います。50本を祈りながら左手と右手に分けて、左手にある筮竹(ぜいちく)の数を8で割ったあまりの数で八卦による卦が決まります。この操作を二回繰り返すので64通りの占い結果が得られます。そして最後に同じ操作をもう一度行います。しかし今回は6で割った余りの数を調べます。八卦は三本の線で作られた記号で、二回操作を行ったので六本の線で記号が構成されています。この場合6で割った余りの数は6通りなので、六本の線の下から(得られた数)本目の線の陰と陽を入れ替えるという操作を行っても問題は生じません。これによって得られた64通りの結果で運勢が決まるというものが略筮法による占い方法です。
遙か昔から二進法があり、合同式(あまりに着目した考え方のこと)を使っていたことには驚きですね。私は数学科に所属しているということもあって、このように試行錯誤することによって数学の礎ができていったのだと思うととても感動します。皆様も是非好きな占い方法を調べて見つけてみてください。

八卦独判断