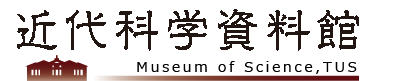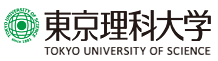資料館スタッフブログ
占いについて
こんにちは、近代科学資料館学生スタッフのK.Kです。今日は東京理科大学の創設者の内の一人である玉名程三が、晩年に研究していたという占いについての記事を書いてようと思います。占いとは何かの運勢を推測することを言います。占いは黄帝の時代(周王朝の紀元前770年よりずっと前)から行われていました。当時は五行という(木、火、金、土、水)の五つの要素からなる理論を用いて自然の運勢を推測していました。人類は昔のほうが先のことへの不安が強かったのかもしれません。そのためか、あらゆる時代のあらゆる場所で占いが行われてきました。占いとは人々の精神的な支えであったと推測できます。
一方で、宗教や社会的な理由で占いが弾圧対象になってしまった例もあります。16世紀ごろ、マルティン・ルターが宗教改革を唱えてから、ヨーロッパ中で魔女禁止法が制定され、占いや予言が禁止されてしまいました。精神的な支えであった占いを疑い、弾圧するという一種の矛盾が生じているように思います。ただ一つ言えるのは精神的な安定を求めていたということです。
占いとは、運勢を占うことによって人々の精神的な支えになっているのだと思います。科学革命が起きて、研究が進んでいる現在でも存在している占いというものは人類に欠かせないものなのかもしれませんね。
以下の本を参考にしました。
・『占いの原点 易経』 梶川敦子著(青弓社) 2008/2/1
・『占術 命・卜・相』 占術隊著(新紀元社) 2011/12/21

おみくじ