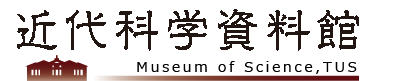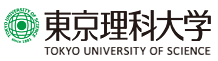資料館スタッフブログ
次の企画展
資料館学生スタッフのS.H.です。私は今、次の企画展に向けて東京理科大学の前身である東京物理学校の創設者の一人である、三輪桓一郎、及び三輪に関わるある事件について調べています。三輪桓一郎は明治13年7月に東京大学仏語物理学科を卒業し、東京大学助教授、独仏留学などを経て、京都大学教授となります。
そんな中、大正2年5月9日東北大学総長だった教育学者、沢柳政太郎が京都大学総長に転任されます。そして同年7月12日三輪桓一郎を含む京都大学教授7名に辞表を提出させます。法科大学はこの事態を重視して協議会を開催し、大学の自治、学問研究の自由の立場から、7月13日総長に口頭で抗議します。しかし、総長は難色を示し、これに応じて協議会は、教授任免においては教授会の同意が必要であるという旨の意見書を作成し、これを総長に提出しました。が、総長はこの意見書には不賛成とし、法科大学と総長との対立は激化、大正3年1月14日ついには法科大学教授、助教授19名による連帯辞職が行われます。その後、各分科大学、法科学生、東大法科等の支援もあり「教官の任免に付総長が其の職権の運用上教授会と協定することは差支なく且つ妥当なり」ということを文相が承認することになります。この一連の流れは沢柳事件と呼ばれ、大学自治の歴史における重要な事柄であるとされています。
今の段階では、この事件の発端、沢柳の免官においてはその7名が選ばれた理由が谷本富を除いて、よくわかっていません。(谷本富に関しては沢柳と同じ教育学者で学者として軋轢があったとされています)これから、三輪桓一郎がなぜ免官されたのか、沢柳と谷本との対立を追いながらその理由を調べます。
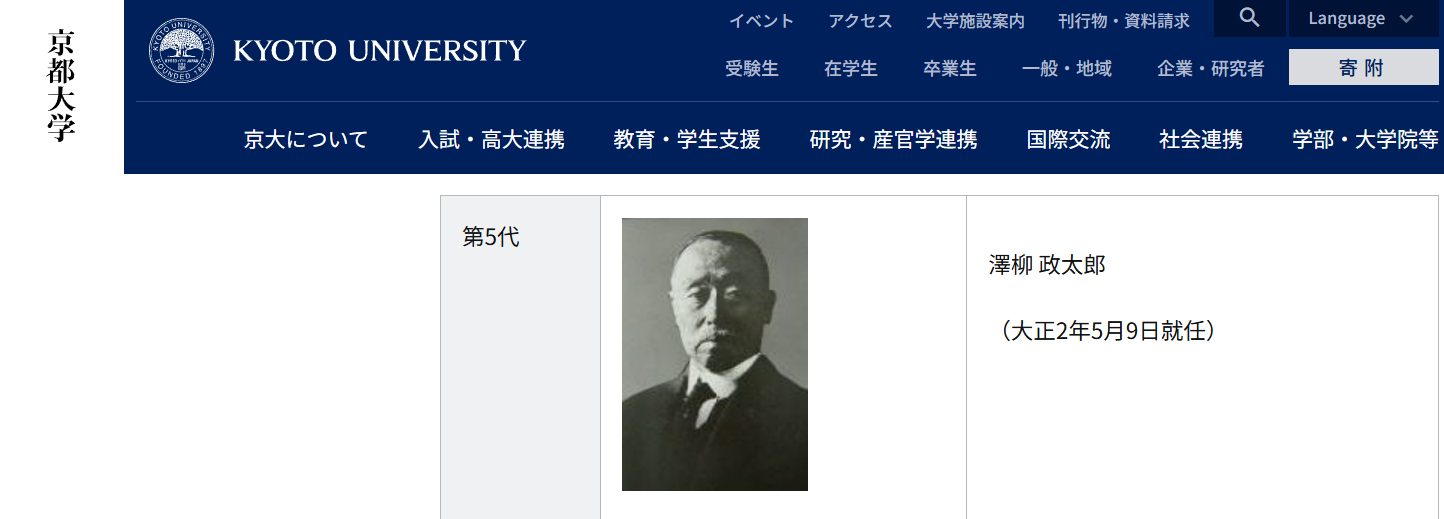
柳沢政太郎