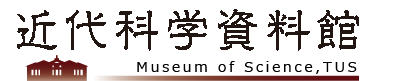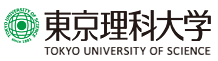資料館スタッフブログ
エスペラント語の普及
資料館学生スタッフのS.H.です。私は今、新しい展示に向けて明治後期から昭和初期の日本におけるエスペラント語について調べています。エスペラント語とはポーランドの眼科医ザメンホフによって、1887年に公表された言語で、エスぺランティストと呼ばれるエスペラント語話者は、世界に100万人ほど存在するといわれています。ザメンホフの生まれたロシア領ポーランドでは、ユダヤ人、ポーランド人、ロシア人、ドイツ人などが混在していました。そこにおいて、民族間の理解や寛容は薄く、その壁を取り払い、人々が人々を理解しあうために、共通言語としてのエスペラント語を作りました。
明治後期から昭和初期の日本におけるエスペラント語の普及について調べて、面白いと感じたのは、その普及にかかわった人の中に今でも有名な、文化人であったり、思想家がいることです。明治時代では、小説家の二葉亭四迷(日本初のエスペラント語の教科書を出版)や社会主義者の大杉栄(エスペラント語学校の講師を務めた)、堺利彦(社会主義機関誌にてエスペラントに関する記事を掲載)、大正時代では、東京物理学校第2代校長で気象学者の中村精男(日本エスペラント学会初代理事長)、昭和時代では、民俗学者の柳田國男(日本エスペラント学会顧問)などが、それぞれの時代でエスペラント語の普及に貢献しました。
このような文化人同士の繋がりを作るのにもエスペラント語は活躍しました。バックグラウンドの異なるエスペラント語を広めるという共通の思いに心血を注いだ時間は、かけがえのないものだったと思います。
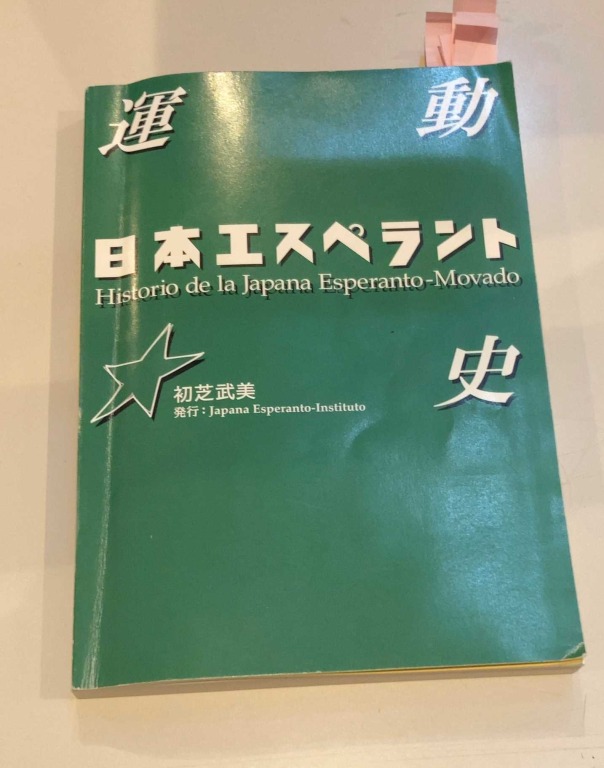
日本エスペラント運動史