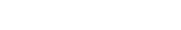「大学で学んだ生物統計学の専門知識を生かせる現在の職に就くことができ、本当に良かったと感じています」
日本では、毎年100品目を超える新医薬品が厚生労働省で承認される。これらの新医薬品や医療機器はすべて、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA)のもとで審査され、有効性・安全性が認められたのち、一般の人々が使用できるようになる。PMDAの新薬審査部に所属する三枝さんは、工学部情報工学科の出身。統計学の知識を生かしながら、医薬品の承認審査や、製薬企業などに対する治験相談の業務に携わっている。三枝さんは言う「医薬品が世の中に出る前には、製薬企業などにより臨床試験が行われます。私の所属する審査部では、これから実施する臨床試験の計画を確認し、承認申請に向けてより良い開発とするために助言をします。承認申請された後は、申請資料やデータに基づき医薬品の有効性や安全性、効能・効果や用量・用法の適切性などを評価します」。
審査部の中で、三枝さんは生物統計担当として活躍している。医薬品の開発においては医学や薬学の観点が重要となる一方で、薬の有効性を科学的に証明するためには、三枝さんが担当する生物統計の考え方が欠かせない。「生物統計学とは、医学や薬学の分野で、生き物に関するデータから科学的な根拠を導くために用いられる統計学です。臨床試験の統計解析や被験者数の検討をはじめ、臨床試験の計画、実施、解析、結果の解釈など、医薬品開発のあらゆる場面で関わります。効果のない薬を誤って効果があると判断しないためにも、臨床試験の計画の段階から慎重に検討する必要があります」。大学時代は主にプログラミングやソフトウェア設計を学んでいた三枝さんが、医薬の世界に興味を持ったのも生物統計の講義がきっかけだったという。「臨床試験では倫理上・実施上の制約を伴うことが多く、その中で薬の効果を適切に評価するために生物統計学は重要だと考えます。生物統計学については寒水研究室に入ってから主に学び始めましたが、そこで身に付けた専門性が生かせる今の職業に就くことができて本当に良かったです」。働き始めて4年目を迎え、担当する疾患分野の知識や規制についても学んでいるという三枝さんの今後の活躍が楽しみだ。

パンフレットには刷新されたロゴが反映されている。 安心感・信頼感・挑戦する意志を表現した。
卒業生のホンネメッセージ
~学生時代を振り返って~
私は6年間、葛飾キャンパスで学生生活を送りました。中でも特に印象に残っているのはキャンパスの「開放感」です。キャンパスは塀で囲まれておらず、建物の入り口はガラス張り。敷地内では犬の散歩をしている方がいたり、図書館前の池では子どもたちが遊んでいたり、地域の方が食堂を利用していたりと、とてもオープンな空間であることに驚きました。入学当初は、いわゆる大学らしいキャンパスに憧れもありましたが、授業や研究に追われる日々の中で、キャンパスを散歩したりベンチでひと息ついたりする時間がよい気分転換になっていました。今振り返ると、のびのびと過ごせた心地よい環境だったと思います。