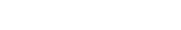建築の枠にとらわれず、デザイン、アートなど多岐にわたる活動で注目を集め続ける鈴野浩一さん。
その原点は、一つの建築模型だったという。
「中学時代、家庭教師の先生が横浜国立大学で建築を学んでいる方で、課題で制作した建築物の模型を持ってきて見せてくれたんです。僕は幼いころから図画工作が大好きだったので“大学生になっても模型作りができるなんて、なんて素晴らしいんだろう”と思ったのがきっかけですね。夏休みの自由研究で、その先生に教わりながら自分の家の模型を作ったんですが、それを先生や同級生に褒めてもらって、すっかりその気になったんです」
漠然と抱いていた建築家の夢は、大学進学を前にくっきりとした輪郭を描き始める。大学付属の中高一貫校に在籍していたが、違った環境で建築を学びたい一心で、必死で受験勉強に励んだという。その甲斐あって、晴れて東京理科大学に入学するが……。
「入学時に教授から最初に言われたのは“建築学科には学生が100人ぐらいいるけれど、この中から建築家が1人出れば上等だ”という言葉。それほど狭き門だということです。でも、理科大で仲間たちと切磋琢磨しながら学んだ経験は刺激的でした」

卒業後は、国内外の建築事務所勤務を経てトラフ建築設計事務所を設立。独立後、最初に手掛けたプロジェクトが鈴野さんの名を世に知らしめた。老朽化したホテルの長期滞在用客室をリノベーションした『テンプレート イン クラスカ』だ。
「ホテルの部屋って、人が入ってモノが置かれていくと、そこから散らかってしまいますよね。でも、モノを収納するスペースがテンプレート化されていれば、例えば使い終わったドライヤーも自然に元の場所に戻すでしょう……そんなふうに、最終的には人も含めて風景ととらえた上で“整理された空間”を提示できるのではないかと考えたんです」
現在はインテリアや舞台美術、インスタレーション(空間構成)にまで活躍の幅を広げる鈴野さん。最後に、後輩たちに向けてメッセージをお願いした。
「僕は仕事をするとき、与えられた条件から、最初に自分なりの“問い”を立てるんです。そして、それを解決することがデザインだと思っています。高校生までは“問い”は与えられることが多いけど、大学に入ってからは自分で“問い”を立てるトレーニングを積んでほしいですね。それは“地球環境問題”なんていう大げさなものである必要はなくて、日々の暮らしの中で感じる“ちょっとした不快感”でもいいんです。自分自身の言葉で“問い”を立て、それに対して自分の立場からどんな“回答”を導くことができるかを考える……それを突き詰めていくことで、自分らしさが生まれてくるのだと思います」