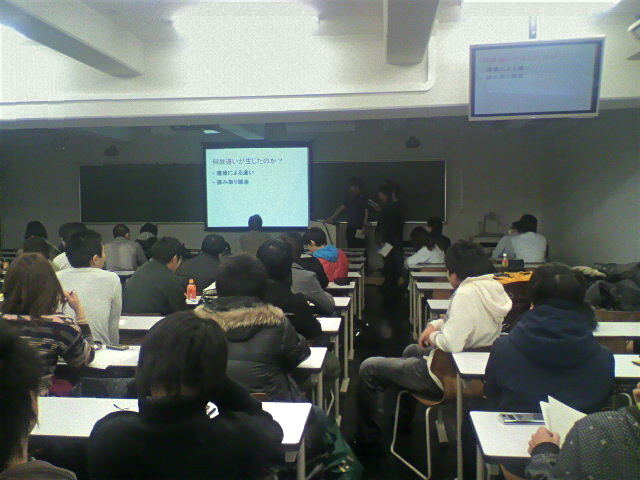私の授業改善
目黒 多加志(理学部第二部 物理学科 教授)
大学の物理学科に入学する学生でも、高校時代に物理実験を経験していない学生も多くいます。そのため二部物理学科の初年次の物理実験では、実験遂行に必要な基礎技術を習得するための講義・実習の時間を5週間程度設けており、また実験だけでなくレポート作成に関しても初めてという学生がほとんどであるため、レポート作成に関しての講義もその中に織り込んでいます。ただ、2年生以降の学生のレポートやプレゼンテーションを見ていると、1年生の内容が身についていない学生も少なくなく、基礎技術をしっかりと習得できるように、試行錯誤の段階ではありますが、昨年度から大幅に変更を加えています。具体的には、(1)時間の拡張、(2)実験と並行した講義の設置(班によって実験、講義が週で分かれる)、(3)1年生でのプレゼンテーションの実施、の3点が大きい変更点となっています。
実験で得られた結果に対し、「なぜ?」を考えることは重要ですが、同様にレポート作成やプレゼンテーションでも常に「なぜ?」を意識することも重要と考えています。エクセルを用いれば何も考えずにグラフができるため、昔よりもこの部分が欠如している場合も少なくありません。しかし《コンピュータの設定》=《他人が理解できる》ではなく、グラフを作成する学生に「なぜ?」の意識が無いと、理解しづらいグラフやレポートになりがちです。例えばグラフ作成の講義では、エクセルのデフォルトで作成したグラフを最初に提示し、間違い探しの形で学生と対話形式でグラフを修正し、それを導入として「なぜ?」を意識できるように講義を行っています。 レポート作成でも多くの学生が文章で結果を説明する事に慣れておらず、箇条書きが多用されている場合も多いため、今年度後期から《模擬レポート》をも計画しています。これは、こちらから与えたデータを元にレポートを作成するのですが、与えるデータを考察に最適な形にし、考察すべき事項も明示しておくことにより、学生はレポートの作成自体に注力できると考えています。
プレゼンテーションに関しても1年生から実施する事により、レポート作成との対比で常に考えられるので、「なぜ?」をより意識することができると考えています。同じ内容であってもプレゼンテーションではレポートと違う表現が適している場合も多く「、なぜ?」が欠如していると単にレポートの焼き直しになってしまい、プレゼンテーションとしては理解しづらい場合が多くなります。したがって、最初に「絶対に行ってはいけないプレゼンテーション」を見せ、やはり学生との対話形式での間違い探しを講義の導入に用いています。
研究所から理科大に移って4年目でまだ試行錯誤も多く、現時点で明確な授業改善とまでは至っていませんが、いわゆる「暗記」から「考える」への転換を、「なぜ?」を意識させることによりスムーズにしたいと考え、現在は1年生の物理実験で試みを開始したところです。
写真は昨年度の1年生のプレゼンテーションの様子ですが、当初考えていたよりも随分とレベルの高い発表もありました。