経営学研究科技術経営専攻(MOT= Management of Technology)は、2024年で開設21年目、これまでに1000名近い修了生を輩出しているビジネススクールである。平日は19時から授業がスタート、土曜日は終日授業を行っていて、 20代から60代まで、文系だけではなく理系出身者も数多く、多種多様な業界・職種の社会人学生が集まっている。2年の在籍期間のうち、1年次後半から教員の研究室 (ゼミ)に全員が所属し、技術経営に関連する研究を行い、その成果をグラデュエーションペーパー(≒修士論文)へと仕上げていく。学生自身の実務に関連する課題などについて、原因分析や解決策の提案を試みる論文が多く、現実の改革に繋がるケースもあるという。MOTの最大の特長は、所属する学生の豊富な実務経験と多様性だ。そのため、自社事例を題材にしたレポートによる議論など、この特長を生かす仕組みを展開している。岸本講師は言う「実務家は、理論を自社や自身の経験に当てはめて何かをするという経験をしたことがない人がほとんどです。しかし、授業で何回かやってみると、こんなふうにやっていけばいいんだと分かり、 あとは自走しながらレベルアップできるようになります」。

岸本講師が日本企業の海外展開について研究をするようになったのは、山形の中小企業からインドネシア進出に関する講演を依頼されたことがきっかけだ。その当時、すでにあった海外展開や国際経営の理論は、欧米企業の経験からつくられたものがほとんどで、日本企業の実例を見て理論構築する必要性を感じたという。『海外展開基礎理論』では、“新興国への海外展開に成功している日系企業の共通点”などがテーマとして扱われている。授業のパターンはいくつかあるが、基本的な流れは、1テーマとなる理論を事前に読む、2自分の仕事に当てはめたレポート等を書く、3それを全員と共有する、4授業でレポートについて議論する。つまり、学生には自分の実務経験に関連した事例を紹介する事前課題が課せられ、それを活用したディスカッションが授業の中で行われるのである。岸本講師は言う「そうすることで、職種や職位の違う学生たちが受講生という一つの組織になり、提供された理論を試行錯誤的に活用することで血肉化ができるのです」。岸本講師の担当講義では、どの科目においても基本的な授業の流れは変わらない。そのため、理論を実践化する訓練が何度も繰り返されることになる。
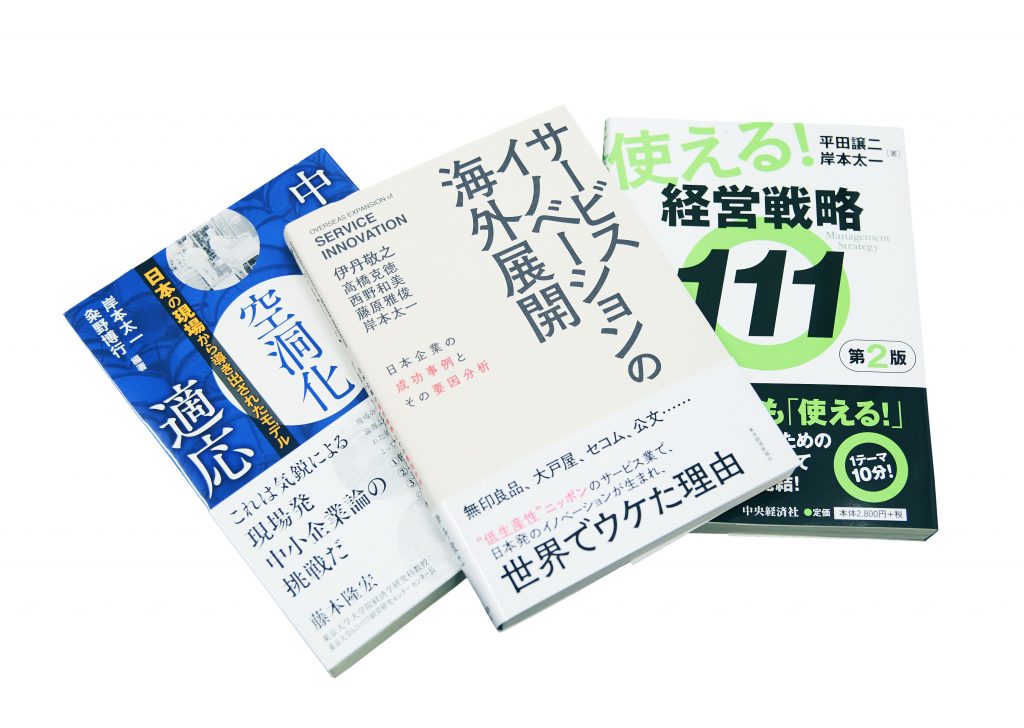
学生たちからのコメントを見てみると、「いろいろな学生たちのケースを知ることで理論の理解に役立ちました」、「担当している仕事で、海外展開で学んだ便益とコストのフレームワークを使わせてもらいました」など、さまざま。理論を実践で使えるようになるには、ある程度の鍛錬や時間は必要なようだが、それを目指した学びを行うことは、刺激的であることは間違いないようだ。「学生には、自分や自社の課題をどんどん持ってきてほしいと思います。ここには、いろいろな会社の人が学ぶという目的で来ているので、利害関係が一切なく、ノーガードで議論できると思います。学生が学生を手助けすることもできるし、教員も一方的に教えるだけではなく、整理して、方向づけてあげることもできる。そういうタイプのビジネススクールだと思っています」と岸本講師。技術と経営の融合でイノベーションを起こすというのが、MOTの大きなテーマである。悩みや課題を抱えた学生たちが、その重要な担い手になっていくのだと、強く感じた。
■ 主な研究内容