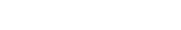「高校時代から勉強が大嫌いでした(笑)
でも、数学だけは好きだったんです」
理科大を受験した理由について聞くと、佐藤隆信さんは冗談めかしてこう答えた。
大学卒業後、佐藤さんは電通を経て新潮社に入社。その後、社長に就任した頃から、ネット通販や電子書籍の登場など、出版界の状況は大きく変わり始めた。
「当社のような老舗出版社では、良質なコンテンツを生み出すノウハウや人材は社内に蓄積されています。それらを時代に即応してどう売っていくかというところで、私が理科大や電通で学んだことが、少しは役に立っているのかなと思います」
その一つが、大学時代にプログラミングを経験し、“デジタル的思考”を身に付けたこと。もう一つは電通でのセールスプロモーションの経験だという。
「従来なら、大まかな方向性だけを定めて、あとは現場に任せるほうがうまくいくケースが多かったと思うのですが、現在は、めまぐるしく変化するメディア状況を見て、個別具体的に、かつスピーディーに判断を下していかなればなりません。これまでにはない新しい発想が必要とされています。その際には、入社前の経験がその新しい発想につながることもあります」

従来の出版社にはない発想、といえば、2014年に神楽坂にオープンした商業施設「ラカグ(la kagu)」は、その好例と言えるかもしれない。この施設は、新潮社がかつて使っていた倉庫を改装したもの。「衣食住+知」をキーワードに、上質な家具や生活雑貨を扱う傍ら、新潮社が主体となって企画・運営する「sōko(ソーコ)」というレクチャースペースでは、作家たちのトークショーや小さな展覧会などのイベントも開催している。
「私が入社した頃には、“作品の持つ実力どおりに本が売れている”という実感がありました。しかし現在では、本来もっと売れるべき本が、そのポテンシャルどおりに売れていない状況にある。これでは本がかわいそうです。「la kagu」のような出会いの場を通じて、伝えるべき人に情報を伝え、きちんと売れる状況をつくっていきたい。まずはリアルなイベントを通して、本との新しい出会い方を発信していきたいと思っています」
理科大の後輩たちにメッセージを、とお願いすると、こんな答えが返ってきた。
「理工系の学生にこそ小説を読んでほしいと思っています。文学を味わい、感性を磨くことで人生は豊かなものになる。ぜひ学生のうちに、豊かな読書体験をしてほしいですね」