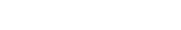課題の本質に斬り込め……
現在、文部科学省で学校施設の防災対策に携わる西村さんが、仕事で壁にぶつかったときに決まって思い出すのは、恩師の、この言葉だという。
その恩師とは、理科大時代の指導教官だった寺本隆幸教授(現・本学名誉教授)。鋼構造建築物の耐震・制振設計を専門とする寺本教授は、日本を代表する建築設計会社・日建設計の構造設計室長から本学教授に転身したばかりの時期だった。
「構造設計の第一人者として、95年の阪神・淡路大震災を経験された先生の指導には重みを感じました。たいへん厳しい方で、“課題の本質に斬り込まなければならない”が口癖でした。就職して15年目になりますが、仕事を進めていく中で困難に直面したときに、ふと立ち止まって“この問題の本質は何だろう”と考えている自分に気付くことがあるんです」
高校時代、物理が得意で“物理を生かせる実学を目指したい”という思いから建築学科に進んだという西村さん。多くの学生たちが卒業後はゼネコンや設計事務所へと進む中で、文部科学省という異色の就職先を選んだ理由は何だったのだろうか?

「文科省の仕事の領域は、教育、科学技術、文化、スポーツなど多岐にわたります。2020年の東京オリンピック・パラリンピックもそうですが、“前向きな人たちを応援する省庁”である点にやりがいを感じています。真っ白な図面、まっさらな土地に建物をイチから造り上げていく仕事も、もちろん魅力的ですが、私は、建築を足掛かりにして、もっと幅広く社会に貢献できる仕事がしたい、と思い文部科学省を選びました。理科大で学んだ建築の知識を、多くの人たちのために役立てることができたら幸せですね」
そんな西村さんに、後輩たちへのメッセージをお願いした。
「日々仕事をしている中でつくづく感じるのは、“仕事には唯一の正解はない”ということ。仕事の答えは自分自身で創っていくものなんです。ゴールに到達するためには、専門的な知識はもちろんですが、目の前の課題に対して自分がどう斬り込んでいくか、そのプロセスを考える力が必要です。アプローチには個性が表れます。自分自身の力でぐいぐいと引っ張っていく人もいれば、周囲の意見をうまく調整しながら進めていく人もいる……自分はどんなタイプのアプローチが得意なのか、その“得意技”を、学生時代に磨いてほしいと思います」