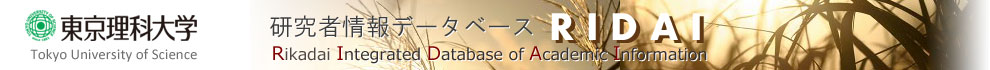ツカモト ヨシミチ
塚本 良道
教授
東京理科大学 創域理工学部 社会基盤工学科
| 研究室名 |
塚本研究室
|
| トピックス |
砂地盤の液状化
|
| 専攻分野 |
地盤工学
|
| 研究分野 |
土質力学/動土質力学/土質工学
|
| 紹介 |
1995年1月の神戸地震(阪神淡路大震災)、2004年10月の新潟県中越地震や2011年東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)では、甚大な地盤災害による社会基盤の多大な損傷が生じ、自然斜面の崩壊で村落の孤立化や宅地盛土の崩壊が生じました。また地震時の砂地盤の液状化や、それに伴う地盤の流動により、護岸構造物にも多大な被害が生じています。地震により飽和砂質土がどのように液状化に至り、地盤の流動を引き起こすかを室内試験や現地調査により研究を行っています。
|
| 研究テーマ |
-
内部侵食現象が砂地盤の液状化抵抗に及ぼす影響の定量的評価法の構築
地盤内の細粒分の移動現象をともなう内部侵食が、砂地盤の液状化に対する抵抗に大きな影響を及ぼすことが知られてきている。本研究テーマでは、内部侵食現象が砂地盤の液状化抵抗に及ぼす影響の定量的評価法の構築を、室内試験を利用して目指す。
-
排水促進による液状化対策技術の開発に関する室内試験
戸建て住宅の液状化対策工法の適用には、さまざまな条件下での適用が必要となってきており、液状化対策工法のオプションを多く整備しておく必要性が高まってきている。本研究テーマでは、簡易排水キットを用いた排水促進による液状化対策技術の開発を目指す。
-
細粒分のフロック化が砂・粘土の力学挙動に及ぼす影響の解明
汽水域・海水域に至ると、粒子の細かい細粒分は、フロック化現象を起こすことが知られている。本研究テーマでは、細粒分のフロック化の大小の程度を、沈降分析を利用して評価するとともに、フロック化の大小の程度が、砂・粘土の力学挙動にどのような影響を及ぼすかを、室内試験を利用して調べることを目的としている。
-
骨格構造に着目した細粒分を多く含む砂質土の液状化抵抗・せん断弾性係数の評価
細粒分を多く含む砂の液状化抵抗の評価は、現在、経験的な手法に頼っており、合理的な推定法の構築が望まれている。本研究テーマでは、砂質土の骨格構造に着目して、骨格間隙比や類似した概念を導入することにより、シルト砂の液状化抵抗の推定法の構築を目指す。
-
液状化リスク評価に及ぼす層間相互作用の影響
現状の液状化リスク評価は、各層を独立に実施されているが、層間相互作用による影響が無視できないという報告がなされてきている。本研究テーマでは、層間相互作用の影響を、室内試験により調べることを目的としている。
|