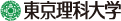こつこつと自分の研究をしていけば、
それで十分
先生が研究者の道に進まれた経緯を教えていただけますか?
大学時代は特に勉強熱心な学生ではありませんでしたが、3年生の後半になって卒論の研究を始めたときに、自分で問題を設定し、情報を調べて問題に答えを与えていくという過程が面白くて大学院に進学することにしました。研究者になることを考えたのは、博士課程に進学するときで、周囲に比べたら遅かったのではないかと思います。
先生の研究テーマとそのテーマを選んだきっかけを教えてください。
私は、顔にあざのある人のライフストーリーを聴くということをずっと続けてきました。なぜ「顔の疾患・外傷」をテーマにしたかというと、きっかけは修士課程の1年の時に見たテレビ番組でした。番組では、顔にあざがある人たちによる自助グループ「ユニークフェイス」の活動が取り上げられていて、当事者の「あざは痛くも痒くもないのに社会的には死んだようなところに追いやられている」という言葉に衝撃を受けました。あざは疾患や外傷といった体の問題ではなく、人と人、人と社会との関係の問題なのだと興味を持ち、これを研究したいと思ったのです。
その当時はルッキズムという言葉もなく、「どうしてそんなマイナーなことを研究するのか」と言う人もいましたが、私が恵まれていたのは、指導の先生や周囲の先輩たちが「それは研究するべき問題だ。あなたは重要なところに目を付けた」と、励まし続けてくれたことです。そういう周囲の励ましのおかげで、「この問題を研究してきちんと形にし、世の中に出そう」と、モチベーションを保ち続けることができました。
博士課程を修了するまでに6年かかっていますが、研究は困難なものだったのでしょうか。
最初私は、外見を「女性の美」の問題としてとらえていました。しかし、それだけでは説明できないのではと、ある時感じてしまったのです。
顔にあざのある人たちから話を聴いていたときに、「あなたもメイクで顔に赤いあざを描いて街を歩いてみたら」と言われ、実際にメイクをして街を歩いてみました。すれ違う人からじろじろ見られるという経験を実際にしてみて、人は私が「美しくない」から見るのではなく、「普通ではない」から見るのだと気づきました。
これまで書いてきた博士論文を、一から書き直さなければいけないと思いましたが、すでに論文はまとめの段階に入っていました。もう一度時間をかけてやり直すべきか、とりあえずこのまま博士論文としては仕上げて、学位を取得してから研究をやり直すかと悩みました。指導の先生に相談すると、「後から時間をつくるのは難しい。今、納得できるまでやったほうがいい」と助言をいただきました。結局6年かけて博士課程を修了。時間はかかりましたが、結果的には遠回りしてでもやり直すべきだったと思っています。
博士課程修了後から今に至るまで、どのような道を歩んでこられましたか?
大学院のあと、東大大学院の経済学研究科に特任研究員としてお声がけいただき、2年半「経済と障害」をテーマにした研究プロェクトに参加しました。私がテーマにしている顔の疾患や外見は、身体の機能制約はないけれど、人の視線や対応など社会的に困難を抱えているという点では障害ととらえることもできます。私はそれまでそういう視点で外見の問題を考えたことはなかったので、とても多くの示唆をいただきました。
その後、同志社大学文化情報学部に助教として5年任期で赴任。私は博士課程のときに結婚していて、この時34歳になっていました。出産も考えていましたが、5年間で実績を上げて次につなげなければという焦りがありました。しかし、心に余裕がないと良い研究もできないものです。結局、この5年間で納得できる成果を上げることはできず、辛い期間でした。
任期を満了し、次に和歌山大学教育学部に准教授として赴任。これから教員になろうという若者たちに、社会的マイノリティや障害などの問題を考えてもらうことは大変意義のあることで、やりがいを感じながら7年間勤めました。
29歳のときに結婚した夫は東京に住んでいたため、3週間に1度くらいの頻度で東京に戻るという生活をしていました。コロナ禍による移動の制限や、お互いに年を取ってきたこともあり、東京で仕事をすることを真剣に考えました。運よく東京理科大学の公募があり、2022年4月から教養教育研究院に採用していただきました。
ワーク・ライフ・バランスはどうされていますか?
研究は、自分で「終わり」を決められないところが難しい。私の場合は子どもがいないこともあって中断する理由がなく、だらだらと仕事をしてしまうのが課題です。ジェンダー論の授業でワーク・ライフ・バランスを教えていますが、自分もまだまだ模索中です。
夫との家事分担は、時間に余裕があるほうがやるという暗黙の了解で分担しています。とはいえ、12年間の別居生活を経て昨年ようやく同居を再開したので、いろいろなことがまだ手探りの状態です。
今後、研究者として目指したいことを教えてください。
私はずっと外見の差別について研究してきました。最初はマイナーな分野でしたが、ここ数年で、「ルッキズム」が注目されるようになり、いろいろなところで議論されています。しかし、これまでの外見差別の歴史や、当事者がどのような想いで「外見差別」と闘ってきたのかを踏まえずに議論されているところもあるように思います。そこを少し整理するような研究ができたら、これまでの研究成果を社会に還元できるのではと考えています。
今後研究者を目指す女性たちへの助言があればお願いします。
私が学生の頃は、女性研究者といえばものすごく立派な方しかいないように思えて、自分があんなふうになれるのだろうかと気が引けていました。しかし私自身は、先生や同僚の研究者、調査協力者など、たくさんの人たちに励まされ支えられながら研究を続けてくることができました。一人の力で切り拓こうと思うと難しく感じますが、人との出会いやつながりを大切にしてこつこつと自分の研究をしていけば、それで十分なのではないかと思います。いろんなタイプの女性研究者がいて当たり前だし、あまり構えなくても大丈夫、と言いたいですね。