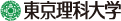でも10%の楽しさがあるから続けられる。
※本ページに掲載されている肩書、所属は取材当時のものです。
先生の現在の研究内容について教えてください。
経営工学の手法を活用して、森林病害虫の防除システムの構築や樹種判別などに取り組んでいます。たとえば、効率的な病害虫の防除策を計画する、ドローンによる空撮画像と機械学習を組み合わせて森林内の樹木の種類を判別する、といったことをやっています。
統計学やデータ分析、情報通信技術などを駆使して、森林資源の持続可能な利用を促進したり、職人技で行われてきた森林管理を最適化するだけでなく、林業従事者の高齢化や人手不足の解決にもつなげようとしています。
先生が森林や林業に興味を持つようになったきっかけは?
子どものころから木とか森が好きでした。加えて、私が子どもだった1980年代は、酸性雨やオゾン層破壊、温暖化など環境問題が注目され始めたころで、私も自然と環境について考えるようになりました。高校のころ、大学の理学部か農学部に進みたいと思っていましたが、やっぱり森が好きだと思い、最終的には農学部林業科に進みました。
その後、ドイツで修士課程を修めておられますね。
研究者になりたいという思いは早くからありましたが、ドイツの大学を選んだのは、日本のみならず世界の林学はドイツ林学を基盤にして発展していたからです。本場で学びたいと思い、フライブルク大学に留学しました。たまたま私は高校のときに第2外国語でドイツ語を学び、大学の一般教養でもドイツ語を選択していたので語学については何とかなると思っていました。それと、ドイツでは前期博士課程はほぼ無償でしたので経済的な理由もありました。
留学時代はいかがでしたか?
1年間は語学研修をしてから大学院に進みましたが、方言の強い先生や、ラテン語を多用する先生もいて、授業のドイツ語は全くわからず苦労しました。友達を作って友達に聞いたり先生に何度も質問に行ったり、とにかく必死でついていきました。1年経つとなんとか聞き取れるようになり、友達も増え、周りの人たちに助けられながらとても充実した大学院生活を送ることができました。特に、実際の森を見に行く野外学習は楽しかったですね。
ドイツでは学生のうちにインターンシップ等の社会経験をすることを推奨しています。私も世界各国の森を見たいと思い、ウガンダやタイ、カナダ、アメリカなどの営林署や民間企業でインターンやボランティアの経験を積みました。
修士課程を終えると、ドイツの材木輸出会社に就職しました。そのまま博士課程に進むよりも一度社会に出て現実世界を知っておいたほうが、広い視野で研究ができると思っていたからです。
働きながら博士課程に戻る道も模索していたのですが、ドイツでは博士課程に進むには自分の研究にお金を出してくれるスポンサーを自分で探してこなければなりません。なかなかチャンスがないまま職を転々としていたのですが、ドイツで後の夫と出会い、帰国後すぐに結婚・出産をしました。
急展開ですね!
夫の実家がある九州に居を移し、フライブルク大学の教授のご縁で九州大学大学院の博士課程に進むことになりました。33歳の時です。もう大学には戻れないのではと思っていましたが、ここからようやく研究者としての人生が始まりました。
博士課程では屋久杉の年輪を分析し、森林動態を研究していました。博士課程修了後、第二子を出産。半年間の育休ののち、ポスドクとして復帰。その後、統計数理研究所で特任助教に。この時に、数理最適化の手法を林業に応用することで、林業に関わる様々な社会課題が解決できるかもしれない!と非常に可能性を感じました。
それが今の研究につながっているのですね。
そうです。2020年に東京理科大学に嘱託助教として着任。2024年4月から創域理工学部経営システム工学科の講師となりました。「林業と経営工学と何の関係があるの?」とよく聞かれるのですが、そもそも経営工学とは、さまざまな社会課題を工学的手法で最適化・合理化・効率化しようとする学問で、案外農林業とは相性がいいんですよ。でもまだ取り組んでいる人が少ないので、研究テーマは山ほどあります。何をやっても新しい局面がある。新しい技術を使って、林業の問題をどんどん解決できたらいいなと思っています。
二児の子育てと研究との両立は大変でしたか?
子どもが小さいうちは毎日忙しくて、ニュースを見る暇も新聞を読む暇もありませんでした。論文も一本も書けないですし、研究どころではない。もう毎日「辞めたほうがいいのかな」と思っていました。でも、求人広告を見ても何の資格もないからできる仕事がない。「大学院まで出て何も仕事がないなんて……」と絶望しました。
そもそも、2人目を出産したのが博士課程を修了した直後で、これから学会や会合にどんどん参加して人脈を作っていかなければいけないというときに、一切外に出られなかったことは痛手でした。研究者として生きていくためには人脈づくりはとても大切だと思います。
理科大に着任してようやく自分の研究室を持つことができ、好きな研究をできるようになりました。落ち込みつつもあきらめなくてよかったと思います。今はとても幸せですね。
先生のご趣味があれば教えてください。
バイオリンですね。柏市の市民オーケストラで演奏をしています。やめたり再開したりを繰り返しながら子どものころから続けています。練習は嫌いなのですが、仲間と良いハーモニーを奏でられたりすると涙が出るくらい感動します。そういう瞬間は、やっていてよかったなと思いますね。
最後に、研究者を目指す学生の方たちにアドバイスをお願いします。
絶対にあきらめず、好きなことを追い求めてほしいですね。ただ、好きなことを仕事にできたからといって、100%楽しいことばかりではない。90%は辛いことの連続です。でも10%の楽しいことがあるから続けられる。学生たちが自分の頭で考えて、自分の好きなことを見つけ、10%を楽しめるスキルを身につけ、幸せな人生を歩んでくれたら嬉しいなと思います。