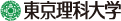たとえ失敗しても好きなことをつきつめたい
先生が心理学を専門にされるようになった経緯を教えてください。
小さい頃から、なぜ人の気持ちは伝わったり伝わらなかったりするのかに興味を持ち、伝わるための方法を開発したいと思っていました。
小学生の頃におまじないがすごく流行りました。中でも、消しゴムに相合傘を書いて、自分の名前と好きな人の名前を書き、その消しゴムにカバーをかけて誰にも見られずに使い切ったら両想いになるというのが、いつも雑誌の「当たるおまじないランキング」1位でした。
なぜそれが1位なんだろう、科学的な根拠はあるのか。おそらく、消しゴムを使うたびに「私、この人のこと好きだわ」とときめいた顔をしたり、相手が通るたびに目線で追ったり、その行動が相手に伝わって、両想いになるのではないか。おまじないという儀式がその人の行動を変えて、それが表情にも表れて相手に伝わるのではないかという自説を立て、それを証明したいと思ったんです。その頃には、将来は心理学で食べていこうと決めていました。
高校の進路面談で、「心理学では食えないぞ」と先生に言われましたが、食べるのに困らない程度稼げればいい。むしろ、自分が謎を解き明かして、市川寛子という名前の論文や、研究成果を世に残して死んでいきたいと思いました。それで心理学の道に進みました。
強い意思をもって大学に進学されたのですね。
筑波大学に入ってから心理学の授業がとにかく楽しくて、一生懸命勉強しました。先生方が私の人生の答えの鍵を握っているんだ!と眩しく思い、一言一句もらさずノートに書きとっていたほどです。
筑波大学は博士一貫課程だったので、迷うことなく大学院に入り博士を目指しました。しかし、論文の精度を高めることに苦戦して、学位取得まで7年かかってしまいました。
その後、学会で知り合った先生のご縁で、中央大学にポスドクとして着任。そこでも私はできが悪く、自分より年下の修士の学生に助言をもらうこともありました。悔しかったですが、ここでの6年間で、自分の専門を深めるスキル、論文を書くスキル、研究者のネットワークを作るスキルをすごく教えていただいて、やっと一人前になれたなと思います。
ポスドクを6年勤められた後、理科大の講師に就任されましたね。
いずれはPI(Principal Investigator)になりたいと、大学の職にいくつか応募しました。ところがどこにも採用されず、30件断られたときには心が折れそうになりました。大学院時代の先輩に相談すると、「俺は200以上アプライした」と。私もそのくらいがんばろうと覚悟を決めた矢先、37件目で東京理科大学に雇っていただけました。
研究者として身を立てるのはかなり難しいのでしょうか。
私は不出来でしたし、キャリアの序盤は自分のことで精いっぱいで、あまり人付き合いを大事にしてきませんでした。しかし、学会に積極的に参加して人の発表を聴いたり、ポスター発表で人脈を作ったり、飲み会のような些細な縁でも大事にしながらいろんな方とお付き合いさせていただくことで、講演の依頼や原稿の執筆などキャリアを作るチャンスが巡ってきました。
自分の努力と相手のニーズやタイミングが合致した時に、「幸運な縁」ができるのだと思います。ですから、「縁」をたまたまのラッキーと捉えるのではなくて、自分の今までのすべての行動から帰結する必然の出来事だと捉えた方が、がんばれると思います。
私が今生き残っているのは、決して私に能力があるからではなく、やめなかったから。好きなことにしがみついてやめなかった。ただそれだけです。
先生のプライベートについても教えてください。
理科大に着任したのち結婚し、出産したのは40歳を超えてからでした。まだ子どもが小さく、大学の講義・研究と育児の両立に奮闘しているところです。
子どもがいることで、以前より自分の研究の時間を確保しづらくなりましたが、理科大には「研究支援員制度」という、未就学児をもつ親が利用できる制度があり、学生に自分の研究をサポートしてもらうことができます。このおかげで私は実験を継続し論文を書くことができ、大変助かりました。
女性の研究者にとって出産のタイミングはとても難しい選択ですね。
体力的なことを考えるなら若い頃に出産をしたほうがいい。しかし、20~30代は最も研究に時間を割くべき時でもあります。私はある程度キャリアを積んでから出産しましたが、逆に大学院のうちに出産し今も研究を続けている人もいます。何が正解とは言えないですね。
お子さんのいる、フランスの男性研究者に聞いたのですが、彼は夕方4時には家に帰って子どもの世話をし、夜8時から自宅で論文を書くという生活をしているそうです。職場では会議があっても夕方4時には終わる雰囲気があるといいます。日本もこういうカルチャーにならないと、仕事と育児の両立は大変だと思います。
これから研究者を目指す学生たちに何かアドバイスはありますか?
学生に博士課程に進むかと聞くと、「自分に才能があれば」「自分に向いていたら」と答える人がとても多いです。でも、向いていようがいまいが興味があるならそのことに自分の人生をかけてみようという遊び心があってもいいんじゃないかなと思います。
「博士課程に行っても結局就職することになったら遠回りだからやめよう」と思うより、「遠回りこそが面白い」と、発想を転換してもいいのではないでしょうか。
もう1つ言いたいのは、研究一辺倒ではなく、趣味は持ったほうがいいということ。私は学生の時からオーケストラをやっていて、今でも続けています。そしてもう1つの趣味は車。大学院の時に親に借金をして買った車に20年以上、今も乗っています。好きな車に乗って、好きな研究を続けられる今の人生をすごく幸せだと思っています。
今後の目標は?
あと20年で退職なので、退職講義で何を話そう、市川寛子は研究者として何を成し得たと言えるか、私の研究にどういう輪郭を与えればいいかと最近おぼろげに考えるようになりました。そこから逆算してこれから20年、自分の研究を進めていくのかなと思っているところです。