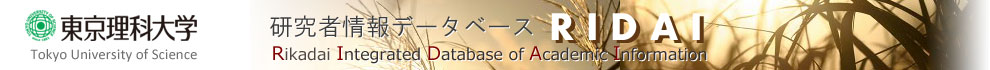化学1‐B及び演習のシラバス情報
| 科目名称 Course title(Japanese) |
化学1‐B及び演習 | 科目番号 Course number |
72CHBAC102 | |
|---|---|---|---|---|
| 科目名称(英語) Course title(English) |
Chemistry 1‐B with Exercises | |||
| 授業名称 Class name |
化学1‐B及び演習 | |||
| 教員名 | 藤本 憲次郎,板垣 昌幸,近藤 剛史,北村 尚斗,寺島 千晶,中山 泰生,石橋 千晶,渡辺 日香里,荒川 京介 |
|---|---|
| シラバスURL | https://class.admin.tus.ac.jp/slResult/2025/japanese/syllabusHtml/SyllabusHtml.2025.9972120.html |