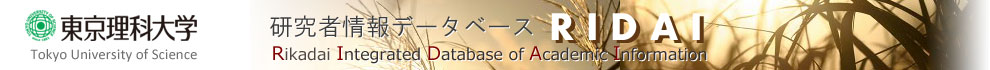文献講読のシラバス情報
| 科目名称 Course title(Japanese) |
文献講読 | 科目番号 Course number |
43ZZZZZ401 | |
|---|---|---|---|---|
| 科目名称(英語) Course title(English) |
Seminar: Reading Practice in Academic Literature | |||
| 授業名称 Class name |
文献講読 | |||
| 教員名 | 和田 正義,安藤 靜敏,宇津 栄三,浜本 隆之,長谷川 幹雄,吉田 孝博,福地 裕,小泉 裕孝,河原 尊之,植田 譲,山口 順之,崔 錦丹,阪田 治,佐藤 俊一,丸田 一輝,永野 健太,白鳥 大毅,山野井 佑介,朱 聞起,栗原 康佑,中里 仁 |
|---|---|
| シラバスURL | https://class.admin.tus.ac.jp/slResult/2025/japanese/syllabusHtml/SyllabusHtml.2025.9943850.html |