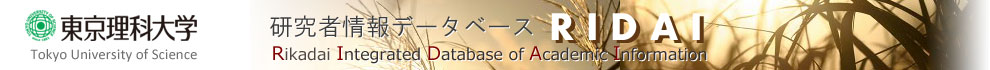医療薬学実習のシラバス情報
| 科目名称 Course title(Japanese) |
医療薬学実習 | 科目番号 Course number |
||
|---|---|---|---|---|
| 科目名称(英語) Course title(English) |
Practice for pharmaceutical health care and sciences | |||
| 授業名称 Class name |
医療薬学実習 | |||
| 教員名 | 真野 泰成,髙澤 涼子,伊集院 一成,嶋田 修治,鹿村 恵明,花輪 剛久,佐藤 嗣道,吉澤 一巳,河野 洋平,鈴木 立紀,野口 耕司,山本 雄一朗,前田 絢子,笠井 智香,中田 亜希子 |
|---|---|
| シラバスURL | https://class.admin.tus.ac.jp/slResult/2025/japanese/syllabusHtml/SyllabusHtml.2025.9931S11.html |