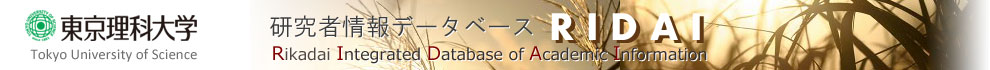Top

イチハラ ガク
市原 学 教授
東京理科大学 薬学部 薬学科
市原 学 教授
東京理科大学 薬学部 薬学科
| グループ |
バイオ、ナノテク・材料、環境 |
| 研究・技術キーワード | 産業衛生学、毒性学、医学、神経科学 |
| 研究・技術テーマ |
|
| 研究・技術内容 | 産業衛生学、産業医学、神経内科学の国内外のネットワークを生かし、産業化学物質による中枢神経障害症例を解析するとともに、動物モデルによる中枢神経障害・認知機能障害作用機序の解明を行っている。研究においては、疫学、動物実験、細胞培養実験などあらゆるレベルの方法を駆使する。国際がん研究機関International Agency for Research on Cancer (IARC)における発がん分類、日本産業衛生学会許容濃度委員会における許容濃度の提案を行うことで世界と日本の公衆衛生政策立案に有用な基礎資料作成に貢献している。症例、疫学研究、リスク・ハザード評価のための委員会活動を通じて抽出された予防医学の問題を解決するための実学的研究を行っている。現在、オートファジー(自食)現象に着目し、産業化学物質による中枢神経障害・認知機能障害の作用機序を解明する研究に取り組んでいる。高齢化社会を迎えた現在、軽度認知症を含めた認知症が65歳以上の4人に1人認められるとの報告が厚生労働省よりなされており、本研究は大きな社会的意義を有する。 |
| 産業への利用 | オートファジーあるいはその不全が中枢神経障害に果たす役割を解明することで、その現象と関わるバイオマーカーの確立を目指している。また、認知障害においてノルアドレナリン神経の障害が認められる例が多く、非侵襲的にノルアドレナリン神経への障害を検出する方法の確立が期待される。私たちの研究では、環境中の親電子性物質がニューロン新生を阻害し、ノルアドレナリン神経繊維を特異的に減少させることが明らかになっている。親電子性を有する化学物質は環境中に多く存在し、その代表例としては、食品中で生成されるアクリルアミド、アクロレインなどが挙げられる。これらの親電子性物質の総量を計測することで、認知機能障害を予防する健康食品を開発することが可能になる。 |
| 可能な産学連携形態 | 共同研究、受託研究員受入、受託研究、技術相談および指導、国際的な産学連携への対応 |
| 具体的な産学連携形態内容 | |
| その他所属研究機関 | |
| 所属研究室 | 薬学部 市原研究室 |
| 所有研究装置 | HPLC (Agilent HP1100), GC-MS (Agilent), Gel Imager, Thermal cycler (PCRおよび定量リアルタイムPCR) |
| SDGs |